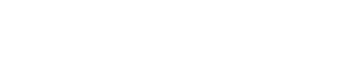糖尿病患者の生活指導から治療のサポートまで、幅広い支援を行う“糖尿病療養指導士”。近年、糖尿病患者数の増加に伴い、この資格を持つ医療従事者の需要が高まっています。
この記事では、糖尿病療養指導士の概要や資格を取得するメリット、資格取得の流れについて解説します。糖尿病療養指導のエキスパートとして、医療現場で活躍したい人は参考にしてみてください。
糖尿病療養指導士(CDE)とは
糖尿病療養指導士は、糖尿病患者の治療とケアに特化した資格です。この資格は一定の経験を積み、認定試験に合格した人に対し、日本糖尿病療養指導士認定機構が認定します。
糖尿病治療では、食事や運動など生活習慣の管理、服薬管理、血糖コントロールなど、患者の自己管理が非常に重要となります。糖尿病療養指導士は、その管理や生活指導のエキスパートとして、患者の指導やサポートをする役割を担うのです。
糖尿病療養指導士は看護師だけでなく、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士も取得することができます。有資格者は全国に約1万7千人で、そのうち看護師・准看護師は約7,500人にのぼります(2024年6月現在)。
参照元:CDEJとは – 一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構
糖尿病療養指導士の資格は2つある
糖尿病療養指導士の資格には、“日本糖尿病療養指導士(CDEJ)”と“地域糖尿病療養指導士(CDEL)”の2種類が存在します。
これらは略称で呼ばれることもよくあります。日本糖尿病療養指導士(CDEJ)は、糖尿病療養指導士(CDE)の末尾に、日本(Japan)の“J”が、地域糖尿病療養指導士(CDEL)には、CDEの末尾に地域(Local)の“L”がついていると考えると覚えやすいでしょう。
それぞれの違いを表にまとめました。
| 日本糖尿病療養指導士(CDEJ) | 地域糖尿病療養指導士(CDEL) | |
| 認定する団体 | 日本糖尿病療養指導士認定機構 | 各地域の認定団体 |
| 対象の職種 | 看護師 准看護師 管理栄養士 薬剤師 臨床検査技師 理学療法士 | 左の6職種に加え 医師・歯科医師 歯科衛生士・介護福祉士など |
| 試験の内容 | 全国共通 | 地域により異なる |
日本糖尿病療養指導士は、日本糖尿病療養指導士認定機構が認定する資格です。資格を取得するには、全国共通の研修や試験を受けて合格する必要があります。そのため、資格を持つことで高水準の知識とスキルが備わっているという客観的な評価にもつながります。
一方、地域糖尿病療養指導士は、各地域で設立された団体により認定される資格です。養成団体は全国で55団体、各都道府県に少なくともひとつの団体があり、それぞれの地域で糖尿病患者の支援活動を行っています。受験可能な職種も、日本糖尿病療養指導士より幅広くなります。
なお、この記事では、日本糖尿病療養指導士について詳しく解説していきます。
参照元:CDEネットワーク|公益社団法人日本糖尿病協会
地域糖尿病療養指導士 認定対象となる職種
糖尿病療養指導士を取得するメリットとは?
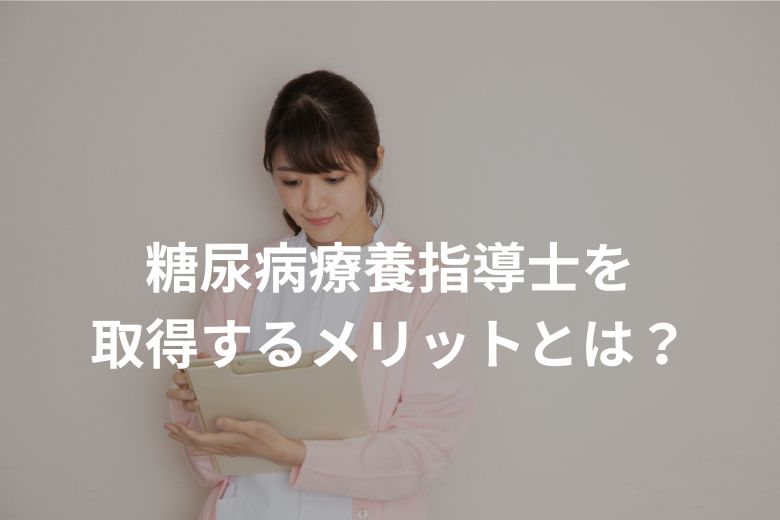
糖尿病療養指導士の資格を取得することで、看護師としてのキャリアは大きく広がります。具体的なメリットを、以下の3つのポイントに分けて解説します。
● 糖尿病に関する高度な知識を身につけられる
● 職場により資格手当がもらえる
● キャリアアップや転職に役立つ
それぞれ詳しくみていきましょう。
糖尿病に関する高度な知識を身につけられる
糖尿病療養指導士の資格を取得する過程では、糖尿病に関する最新の医学知識や治療方法、糖尿病患者の療養指導に関するスキルを学びます。これらの知識とスキルを臨床現場で活用し、経験を積めば、糖尿病療養指導のエキスパートとして活躍していくことができるでしょう。
また、患者一人ひとりへの指導はもちろん、医療スタッフ間で知識を共有することで、チーム全体の看護ケアの質を大きく向上させることにもつながります。専門性の高さを発揮できることで、仕事のやりがいもより感じられるようになるでしょう。
職場により資格手当がもらえる
糖尿病療養指導士の資格保有者に対し、手当を支給する病院・クリニックもあります。資格手当の金額は医療機関によって異なりますが、毎月数千円〜2万円程度の手当を支給するところが多いようです。努力をして取得した資格が給与面でも評価されることは、モチベーションアップにもなるでしょう。
また、病院によっては資格取得や更新のための費用を補助する制度を設けているところもあります。所属する職場の制度を確認してみましょう。
キャリアアップや転職に役立つ
糖尿病療養指導士の資格は、看護師としてキャリアを広げることに役立ちます。
糖尿病療養指導士は更新制の資格です。資格取得時だけでなく、更新の際にも、認定審査をクリアする必要があるため、専門知識やスキルを常にアップデートさせておくことが求められます。そうすることで臨床現場においても、十分な知識とスキルを発揮して活躍できるでしょう。
また「認定資格保有者には糖尿病患者の療養指導に関する専門知識やスキルが備わっている」という高評価を得る機会も多く、キャリアアップにもつながりやすくなるのです。
また、日本糖尿病療養指導士は全国共通の資格です。糖尿病患者の療養指導に携わる職場へ転職活動をする際にも、有利にはたらくことでしょう。
糖尿病療養指導士になるまでの流れ
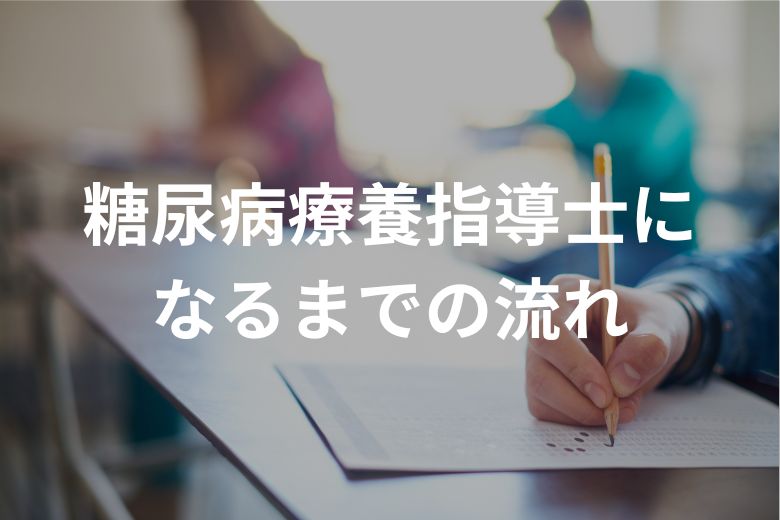
糖尿病療養指導士の資格を取る際には、段階的に準備を進めていく必要があります。ここからは具体的な手順について、以下の4つに絞って解説していきます。
①講習会の申し込み・受講
②受験申込・資格審査
③認定試験の受験
④試験結果の通知・認定取得
参照元:資格取得までの流れ – 一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構
①講習会(研修会)の申し込み・受講
まずは日本糖尿病療養指導士認定機構が主催する講習会に参加申し込みを行い、受講しましょう。講習会はオンライン(eラーニング)で受講できます。2024年度の申し込み時期は7月〜10月、受講期間は10月〜11月でした。
講習会では、糖尿病療養指導士の役割・機能や、糖尿病の治療・療養指導に関する知識を学べます。テキストが指定されているため、自身で用意しましょう。
参照元:講習内容 – 一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構
②受験申し込み・資格審査
講習会を受講後は、認定試験の受験申し込みを行い、資格審査を受けます。審査申し込みの際には、糖尿病療養指導の自験例(指導事例)を10例以上提出しなければなりません。申し込み期間は10月上旬~12月初旬です。
受験を申し込むと資格審査が行われ、審査に通った人は認定試験の受験資格が得られます。認定試験は翌年の3月ごろに実施されます。
③認定試験の受験
認定試験は年1回、全国各地の会場で実施されます。出題形式はCBT多肢選択式で、問題数は120問、試験時間は180分(前半90分+休憩15分+後半90分)です。
試験問題は、日本糖尿病療養士認定機構の 「糖尿病療養指導士ガイドブック」より出題されます。試験対策には、いくつかの出版社が販売する過去問題集や試験対策問題集を利用するとよいでしょう。
④試験結果の通知・認定取得
認定試験の受験結果は、4月末ごろに通知されます。合格者には5月末ごろ、以下の3つが発行され、正式に糖尿病療養指導士として認定されるのです。
● 認定証
● 認定バッジ
● CDEJカード
認定を受けたあかつきには、晴れてエキスパートとして現場で活躍できます。
資格取得後は5年ごとに更新が必要になる
糖尿病療養指導士の資格は5年ごとに更新が必要です。
認定更新を3回行うと、金色の認定バッジを取得できます。金色の認定バッジは、経験を積んだ糖尿病療養指導士である証です。糖尿病療養指導士の資格を取得したら、次は金色のバッジ取得を目指して活動していくと、モチベーションアップにつながるでしょう。
糖尿病療養指導士の受験資格について
日本糖尿療養指導士の受験資格には、いくつかの要件があります。まず、下記のいずれかの資格を有している必要があります。
● 看護師・准看護師
● 管理栄養士
● 薬剤師
● 臨床検査技師
● 理学療法士
さらに、以下の3つの条件を満たさなければなりません。
① 一定の条件を満たす医療機関で、過去10年以内に2年以上継続して勤務し、糖尿病患者の療養指導業務に従事、かつ通算1,000時間以上、糖尿病患者の療養指導を行った経験をもつこと
日本糖尿病療養指導士認定機構が定める“一定の条件を満たす医療機関”は、以下のとおりです。
1. 当該施設に勤務する、以下いずれかに該当する医師が、糖尿病療養指導にあたり受験者を指導していること
● 日本糖尿病学会専門医
● 日本糖尿病学会の会員であり糖尿病の診療と療養指導に従事している常勤の医師
2. 外来で糖尿病患者の診療が行われていること
3. 糖尿病の患者教育や食事指導が恒常的に行われていること
② ①の期間に、糖尿病療養指導の自験例(指導事例)が10例以上あること
③日本糖尿病療養指導士認定機構が開催する講習(eラーニング)を受講修了していること
これらの要件認定の基準日は試験受験年度の12月5日です。12月5日の時点で、「すべての要件を満たしている必要がある」とされています。
参照元:受験資格について – 一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構
糖尿病療養指導士の試験の合格率の目安
糖尿病療養指導士の試験では、「客観試験」「糖尿病療養指導自験例の記録」の両方において一定水準に達している人が合格となります。なお客観試験の評価・「糖尿病療養指導自験例の記録」の評価ともに合格基準は明らかになっていません。
糖尿病療養指導士の試験の合格率は、年度によって変動がありますが、90%台で推移しています。2020年度〜2023年度の全職種での合格率は毎年95%台です。合格率から見ると、試験の難易度はそこまで高くはないといえるでしょう。
参照元:一般社団法人日本糖尿病療養指導士認定機構受験者数・合格者数・合格率
まとめ
この記事では、糖尿病療養指導士の概要や資格を取得するメリット、受験の流れについて紹介しました。
糖尿病患者数は、生活習慣と社会環境の変化に伴い、年々増加しています。医療の進歩とともに糖尿病治療も日々進化しており、新たな薬や治療法が次々と開発されています。それにより、従来よりも患者が自身のライフスタイルに合わせた自己管理ができるようになってきています。専門的な知識とスキルを持ち、患者の指導やサポートを担う糖尿病療養指導士のニーズは、今後もさらに高まっていくことでしょう。
糖尿病療養指導にやりがいを感じる人、資格を取得して専門性を身につけていきたいと思っている人は、糖尿病療養指導士の資格取得を目指してみるとよいでしょう。
看護師の求人探し・転職のことなら「スマイルナース」
糖尿病療養指導士の取得には、医療機関で糖尿病患者に対する療養指導の経験を2年以上積むことが必須です。
スマイルナースでは、あなたの理想のキャリアに合わせて資格取得を目指せる病院・クリニックをご紹介します。また、経験豊富なコーディネーターが、面接対策や条件交渉など、看護師の転職を完全サポートします。専門性の高い職場で活躍するチャンスをつかみたい看護師は、ぜひ一度、ご相談ください。