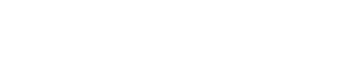看護師として働いていると、心肺蘇生など患者さんの急変に遭遇することは少なくありません。医療機関内で看護師が救命処置に携わるのに役立つ資格に、ACLSプロバイダーがあります。
この記事では、ACLSプロバイダーの概要や資格の取得方法、試験の難易度、メリットについて解説します。患者さんの急変時に慌てずに対応する知識やスキルを身につけたい看護師は参考にしてみてください。
ACLSプロバイダーとは?
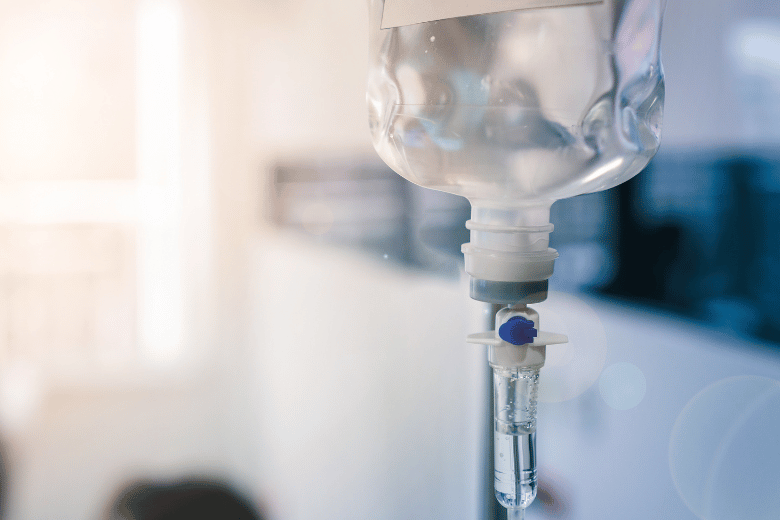
ACLSプロバイダーとは、心肺停止に対して行う二次救命処置に関する知識やスキルを持つことを示す資格です。ACLSは、「Advanced Cardiovascular Life Support」の略で、二次心肺蘇生法を意味します。
一次心肺蘇生法(一次救命処置)と二次心肺蘇生法(二次救命処置)の違いは、次のとおりです。
二次心肺蘇生法:医療機関において、医師などが行う高度なCPR
ACLSで行う二次心肺蘇生法には、基本のCPRに加えて、電気的除細動、高濃度の酸素投与、静脈路確保及び薬剤投与が含まれます。
ACLSプロバイダーが果たす役割
ACLSプロバイダー保有者の役割は、心肺停止の患者さんに対して、適切な救命処置を行うことです。
ふだんの医療現場では、看護師個人に分からないことがあっても、周囲に相談したりマニュアルを参照したりすることができます。しかし患者さんの急変時は一刻を争い、速やかな処置が必要とされるため、実践的な知識やスキルが身についてなければなりません。
ACLSプロバイダーの資格取得を通して、急変時にもパニックにならずに行動したり、経験の浅い看護師に的確な指示したりできるようになります。
ACLSプロバイダーの資格を取得する方法
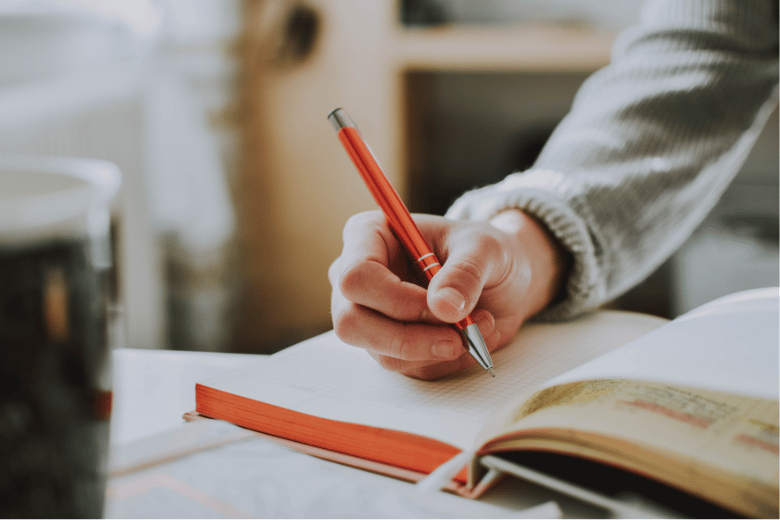
患者さんの急変の起こしやすさは部署によって差があるものの、すべての看護師がACLSプロバイダー資格を保有していれば、患者さんの救命に貢献できます。ここではACLSプロバイダーの資格取得について説明します。
申し込みから資格取得までの流れ
ACLSプロバイダーの資格取得の流れは、次の通りです。
2,指定の教材を購入し、受講日までに予習をする
3,オンラインの“受講前自己評価”課題で正答率70%以上を達成する
4,2日間のコースを受講し、実技と筆記試験に合格する
5,認定カードを受け取る
認定カードの有効期限は2年です。資格の更新には、指定の短期コースを受講します。
1日で修了できるコースもある
ACLSプロバイダーの資格の認定・授与を行っている団体はいくつかあり、コースの受講時間が異なります。AHA(米国心臓協会)が定めるACLSプロバイダーの講習は一般的に2日間にわたって行われますが、1日で取得できるコースもあります。
ACLSの1日コースでは、ビデオ教材の事前視聴など事前学習を行い、コース当日に実技練習やシミュレーションを受けます。勤務先のシフトやスケジュールで、2日間連続の受講がむずかしい人は、1日コースを検討してみるとよいでしょう。
ACLSプロバイダーコースを受講する条件
ACLSプロバイダーのコースを受講するには、AHAの認定するBLSプロバイダー資格の保有者でなければなりません。BLSプロバイダーは、CPR(気道確保・人工呼吸・心臓マッサージ)やAEDの使用といった一次救命処置に関する知識やスキルを持つことを示す資格です。
一次救命処置は、その場でできる基本的な処置であり、BLSプロバイダー資格は医療職でない一般の人でも取得することができます。
受講対象と費用
ACLSプロバイダーの受講対象者は、医師や歯科医師、看護師などの医療従事者です。
患者さんの心肺停止する場面に遭遇しやすいのは、救命救急や循環器疾患を扱う部署であるものの、それ以外の部署でも急変は起こりえます。医療従事者が取得しておくに越したことはないでしょう。
ACLSプロバイダーの受講費用は、コースや団体によって異なりますが、4万円前後に設定されていることが多いようです。
難易度
ACLSプロバイダーの試験の難易度は、それほど高くありません。テキストや実技など受講コースで学んだ内容をしっかり理解できれば、合格することができます。
ただ試験に合格するには、二次救命処置の前提となる一時救命処置の内容と流れ、心電図の判読、薬剤に関する知識のほか、AHAの診療アルゴリズムを理解する必要があります。
筆記試験と実技試験は、2日目の終盤に行われます。合格できるか不安に感じる人は、テキストの内容をしっかり理解しておきましょう。
ACLSプロバイダーで学べる内容
ACLSプロバイダーの受講コースでは、次の内容を学ぶことができます。
治療システム,蘇生科学,体系的なアプローチ,CPRコーチ,テクノロジーの確認,増悪時の臨床兆候,急性冠症候群・急性脳卒中の症例学習,チーム医療,心停止および心拍再開後の症例学習
≪実技≫
BLS,気道管理,徐脈時の処置,頻拍(安定性および不安定性)時の処置,メガコード実習
看護師がACLSプロバイダーの資格を取得するメリット

看護師がACLSプロバイダーを保有することには、いくつかのメリットがあります。具体的にみていきましょう。
急変時に自信を持って対応できる
ACLSプロバイダーの保有することで、二次救命処置の対応を慌てずに行えるようになります。心肺停止のような急激な容態変化は、いつ起こるか予測ができないものです。
臨床経験の長い看護師であっても、患者さんの急変に遭遇していない人もいるでしょう。このような場合、救命処置に関する必要最低限の知識やスキルだけでは、実践的な動きができない可能性があります。
ACLSプロバイダーの取得を通して、二次救命処置の方法や流れを把握しておけば、急変時でも看護師として的確な行動を取りやすくなります。また二次救命処置の内容や流れについて把握することで、看護師自身がパニックを起こさずに、医療チームの一員として関われるでしょう。
キャリアを積むうえでプラスになる
ACLSプロバイダーを取得することで、看護師としてのキャリアップにもつながります。急変対応がしっかりできれば、自身が適切な処置や介助を行えるだけでなく、二次救命処置に慣れていないスタッフにも口頭指示ができます。
患者さんの容体が変化したときは、チームの統率力や的確な判断力が問われます。「急変時に適切な対応や指示ができる」と評価されれば、昇進のチャンスにも恵まれるでしょう。
また、救急医療や循環器疾患の専門分野を極めたい場合には、ACLSプロバイダーの取得過程で身につけた知識やスキルを活かすことができます。
まとめ
ACLSプロバイダーは、心肺停止をはじめ急変患者さんに行う二次救命処置の知識とスキルがあることを証明する資格です。指定のコースを1~2日間受講し、試験に合格することで資格を取れます。
ACLSプロバイダーの取得を通して、医療機関内で行われる救命処置への理解が深まれば、急変時に慌てずに対応できるようになります。患者さんの容体変化はどの部署でも起こりえます。看護師としてしっかり対応するためにも、ACLSプロバイダーの取得を検討してみましょう。
看護師の求人探し・転職のことなら「スマイルナース」
看護職専門の転職サイト「スマイルナース」では、東京都・神奈川県・埼玉県・千葉県及び北海道の求人を扱っています。希望条件に合わせて検索することで、多数の募集求人の中から、自分にぴったりの職場を見つけることができます。さらに、無料会員登録後は、専任アドバイザーから転職サポートを受けられます。
ACLSプロバイダー資格を活かした職場を探している人、急変時の看護を実践できる医療機関を探している人はご相談ください。