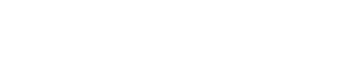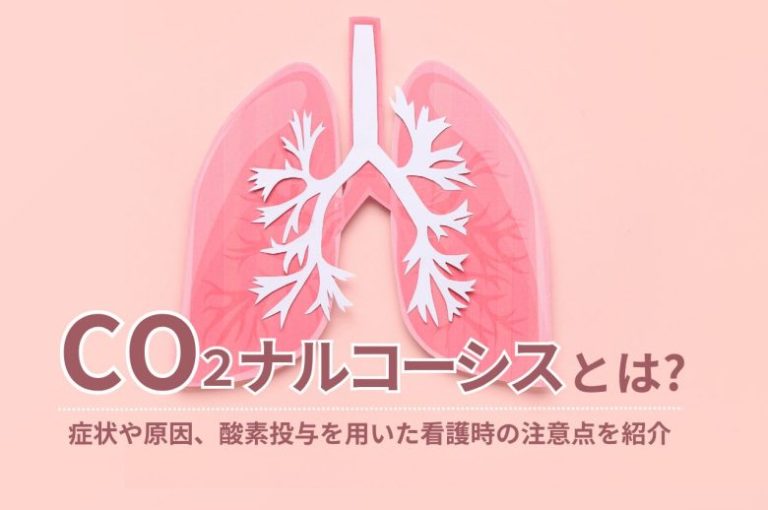CO2ナルコーシス(英語表記:CO2 narcosis)とは、換気障害により二酸化炭素が体内に過剰に蓄積し、意識障害や自発呼吸の減弱を引き起こす病態のことです。
慢性呼吸不全を抱える患者さんに対し酸素投与を行う場合にも発症リスクがあり、看護師は病態について把握しておく必要があります。
本記事では、CO2ナルコーシスの発症メカニズムや原因、観察ポイントについて解説します。CO2ナルコーシスに関する理解を深め、患者さんの観察や酸素管理に役立てましょう。
CO2ナルコーシスとは
CO2ナルコーシスとは、換気障害により体内に二酸化炭素(CO2)が蓄積し、脳が機能低下を起こす病態です。
通常、二酸化炭素は呼気を通じて体外へ排出されますが、呼吸が適切に行われないと、二酸化炭素が体内に過剰に蓄積し始め、「呼吸性アシドーシス」という状態になります。
呼吸アシドーシスは、血液のpHが酸性に傾いた状態で、脳の機能低下を起こします。頭痛や意識障害などの症状がみられ、病態が進むと昏睡状態になることもあるため、早期発見と適切な対応が必要です。
CO2ナルコーシスが起こる仕組み
CO2ナルコーシスが発症するきっかけは、体内における二酸化炭素の過剰な蓄積です。メカニズムを理解するために、まずは呼吸の仕組みと二酸化炭素の性質についてみていきましょう。
生物は呼吸によって体内に酸素を取り込み、細胞の代謝によって生じた二酸化炭素を体外に排出します。通常、二酸化炭素は血液を介して肺に運ばれ、肺で酸素と交換され、体外に排出されます。しかし、何らかの理由により呼吸が正常に行われないと、二酸化炭素をうまく排出できなくなります。
二酸化炭素(CO2)は水(H2O)に溶けやすい性質があるため、その大半は血液中で重炭酸イオン(HCO3)に変換されます。血液に溶け込んだ重炭酸イオンは、赤血球内の炭酸脱水酵素の働きにより、水素イオン(H+)と炭酸イオン(HCO3-)に分離します。
水素イオン(H+)は血液のpHバランスを維持・調整するのに重要な役割を果たします。血中の水素イオンが増加すると、血液が酸性に傾き、「アシドーシス」になります。とくに換気障害に関連したアシドーシスを「呼吸性アシドーシス」といいます。
二酸化炭素の過剰な蓄積から呼吸性アシドーシスになるとCO2ナルコーシスに陥り、意識障害や呼吸抑制がみられます。
CO2ナルコーシスによって起こる症状

CO2ナルコーシスの症状は、病態の進行具合によって異なります。主な症状は次のとおりです。
頭痛や眠気の発生
初期のCO2ナルコーシスでは、頭痛や眠気がみられることが多くあります。
頭痛が生じるのは、血液中の過剰な二酸化炭素により、脳の血管が拡張して頭蓋内圧が上昇するためです。また二酸化炭素の蓄積は、中枢神経の働きの低下も招き、眠気を引き起こします。
判断力や集中力の低下
CO2ナルコーシスにより体内の血液が酸性に傾くと、脳の機能が落ちて、判断力や集中力が低下しやすくなります。周囲の状況把握やコミュニケーションに支障をきたす患者さんもいます。
意識障害や呼吸状態の変化
CO2ナルコーシスがさらに進むと、意識障害が生じ、昏睡状態へと陥ってしまう患者さんもいます。また、酸素の供給が減ることで、呼吸状態もあえぐようになるといった変化が生じます。
CO2ナルコーシスの初期症状
CO2ナルコーシスの主な初期症状は、次のとおりです。
● 頻脈
● 呼吸促迫(酸素不足を補うために、呼吸が速くなる)
● 発汗
● 振戦(企図振戦、羽ばたき振戦)
CO2ナルコーシス進行期の症状
CO2ナルコーシスの進行期の症状は次のとおりです。
● 傾眠
● 昏睡
患者さんがウトウトと傾眠しがちなときは、意識レベルが低下している可能性があります。また昏睡状態や呼吸停止がみられている場合、速やかな救命処置が必要です。
呼吸が止まって酸素供給が滞ると、脳をはじめ体の重要な器官に深刻な影響を与えるためです。
CO2ナルコーシスを引き起こす主な原因
CO2ナルコーシスはさまざまな原因によって引き起こされます。主な原因についてみていきましょう。
換気障害
換気障害があると、二酸化炭素の体外への排出が十分に行われません。換気障害を引き起こす原因には、気道閉塞や肺の換気機能の低下などがあります。例えば、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)のような閉塞性肺疾患を抱える患者さんは、CO2ナルコーシスに陥るリスクが高くなります。
また、睡眠時無呼吸症候群で呼吸停止時間が長くなることも、二酸化炭素の蓄積を招きます。
呼吸効率の低下
呼吸を司る筋肉や神経に障害があると、CO2ナルコーシスを発症しやすくなります。呼吸の効率が悪くなることで、体内の二酸化炭素が排出されにくくなるためです。
脳卒中や神経疾患などにより呼吸機能に問題があると、CO2ナルコーシスを発生しやすくなります。
体内の二酸化炭素の増加
体内の二酸化炭素の増加は、CO2ナルコーシスの直接の原因となるものです。体内に過剰な二酸化炭素が蓄積する原因には、代謝異常や外的要因によるものもあります。
とくに後者については、過度な運動後に呼吸が不十分になる、誤って炭酸ガスを大量に吸うといった状況が挙げられます。
CO2ナルコーシスを引き起こしやすい疾患・状態
疾患によっては、CO2ナルコーシスの発症リスクを高めるものがあります。具体的には、次のとおりです。
● 肺結核の後遺症
● 脳血管疾患、呼吸抑制の副作用のある鎮静剤投与後
● 重症筋無力症、筋ジストロフィー
これらの疾患等により呼吸機能が低くなると、二酸化炭素が蓄積されやすくなり、CO2ナルコーシスの発症リスクが高まります。
CO2ナルコーシスになりやすい人の特徴
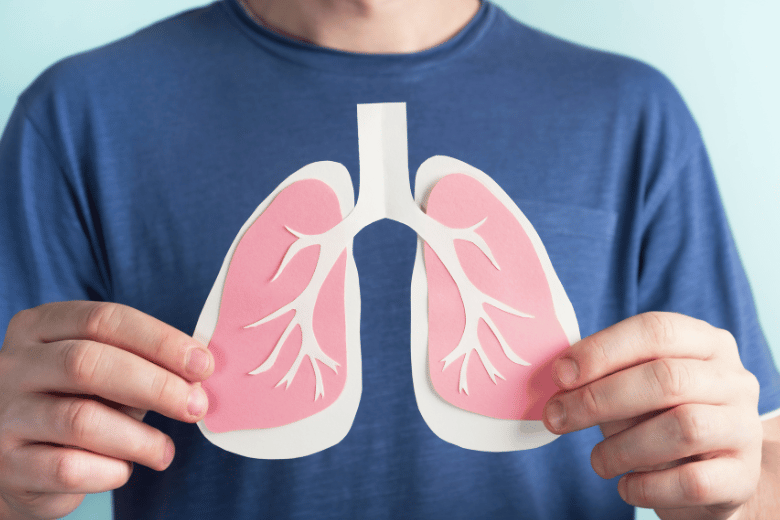
CO2ナルコーシスの発症リスクがとくに高いのは、慢性呼吸器疾患を抱える患者さんのうち、酸素療法を受けている人です。
呼吸のコントロールは血液中の酸素量である酸素分圧(PaO2)と二酸化炭素量である二酸化炭素分圧(PaCO2)によって、脳が行います。しかし慢性呼吸器疾患を抱えていると、血液中の二酸化炭素量が多い状態が続き、脳がそれに慣れてしまい、低めの酸素分圧によって呼吸がコントロールされてしまいます。
酸素投与により酸素分圧が高まると、脳が「酸素が足りている」と勘違いを起こし、呼吸を抑制します。呼吸が弱くなったり、少なくなったりすることで二酸化炭素が蓄積されると、CO2ナルコーシスを発症します。
CO2ナルコーシスを防ぐために看護師ができること

CO2ナルコーシスは、看護師が適切な観察や対応を行うことで、早期発見ができ、病態の進行を抑制することができます。
酸素投与前の既往歴の確認する
CO2ナルコーシスを予防するために、患者さんの既往歴をしっかり確認したうえで、酸素投与を開始しましょう。
とくに換気障害を抱える患者さんへの酸素投与は、慎重に行う必要があります。前述したように、患者さんに酸素を過剰投与すると、CO2ナルコーシス発症のリスクを高めるためです。患者さんの既往歴から呼吸状態やリスクを把握し、酸素投与時にもしっかり観察を行いましょう。
SpO2を90%に維持する(※慢性呼吸不全を抱える患者さんに酸素投与する場合)
CO2ナルコーシスを防ぐためには、患者さんの血中酸素飽和濃度(SpO2)を適切に維持することが重要です。
SpO2は96%以上が正常値であるものの、慢性呼吸疾患を抱える患者さんの場合、90%以上を保つことを目標にすることが推奨されています。低酸素血症を改善しつつ、CO2ナルコーシスの発症リスクを下げるためです。慢性呼吸不全をもつ患者さんに酸素療法を行うときは、過剰な酸素投与を避けなければなりません。
具体的な投与量については、患者さんの状態に合わせて医師が決定します。看護師はバイタル測定時にSpO2測定や呼吸状態を観察し、疑わしい症状があったら、すぐに医師に報告しましょう。また、慢性呼吸不全の患者さんは、離床後にSpO2が下がることが多いため、慌てて酸素の量を増やさないことも大切です。
ただし、喘息の急性増悪など急性呼吸不全の患者さんに対しては、SpO2の正常値を目指した酸素投与が必要です。
患者さんの状態をよく観察する
CO2ナルコーシスを防ぐためには、患者さんの状態をしっかり観察・アセスメントし、異常の早期発見に努める必要があります。
酸素投与中に呼吸状態や意識レベルに変化がみられる場合、CO2ナルコーシスの可能性も考えられます。日々の業務のなかで、患者さんの状態を観察し、小さな変化にも気づけるようにしましょう。
まとめ
CO2ナルコーシスは、体内で二酸化炭素が蓄積し、呼吸アシドーシスに至ることで起こる病態です。症状が進行すると、意識障害や呼吸状態の変化を引き起こし、命に関わることもあります。
とくに慢性呼吸疾患を抱える患者さんは、酸素投与によりCO2ナルコーシスを発症しやすいので、慎重に管理しなければなりません。看護師は患者さんの状態をよく観察し、必要時に迅速な対応を取れるようにしましょう。
参考:
日本循環制御医学会 第39巻 第2号 2018/1.脳循環調節と呼吸調節
日本臨床学会/Q&A Vol.86 CO2ナルコーシスでの意識障害
JACA 日本急性期ケア協会/急性期の呼吸ケアで気を付けること【CO2ナルコーシス】
日本赤十字社 松山赤十字病院/呼吸不全とCO2ナルコーシス
厚生労働科学研究成果ベース/酸素投与量に関してはそれほど過敏になる必要はありません
看護師の求人探し・転職のことなら「スマイルナース」
看護職専門の転職サイト「スマイルナース」では、首都圏を中心に豊富な求人を紹介しています。
働きたい地域や診療科、シフト体制など、あなたにぴったりの職場をご紹介します。無料会員登録後は、専任アドバイザーが転職サポートを行いますので、お気軽にご相談ください。