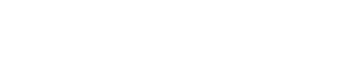介護職は介護が必要な高齢者や障がい児(者)の日常生活をサポートする専門職です。超高齢化社会を迎えた日本では、介護職のニーズは高まり続けています。
今回は、介護職について、給与面にフォーカスして紹介していきます。給与アップや転職を考えている介護職、介護業界への転身を検討している人は、参考にしてみてください。
介護職とは?

介護職は“要介護認定”を受けた高齢者や障がい児(者)の日常生活を支える専門職です。
活躍の場は、高齢者ケア施設や障がい児(者)の自立支援を担う施設、病院など。病院で働く介護職員は一般的に“看護助手”と呼ばれます。
介護職は要介護認定を受けた人が安心・快適で、かつ自立した生活が送れるよう支える役割を担います。
介護職には利用者の日常生活のすべてに手を貸すのではなく、利用者が自分の力で生活できるようサポートすることが求められます。
介護職の主な仕事内容
介護職の仕事内容は大きく“身体介護”と“生活援助”の2つに分かれます。
身体介護は、要介護者の身体に直接触れて行うサポートのことで、食事介助や移動・移乗介助、入浴介助などが該当します。
生活援助は、日常生活を送るのに必要な支援のうち、要介護者の身体に直接触れずに行うものを指します。具体的には、食事の準備や洗濯、買い物、掃除などです。
介護業界の現状とニーズ
超高齢社会を迎えた日本では、介護サービスのニーズも急拡大しています。2025年には団塊の世代の全員が75歳となり、介護の必要な高齢者の数が増大。と同時に介護職の需要もますます高まっています。
一方で、介護業界の人材不足は深刻です。
厚生労働省の試算では、2040年には約280万人の介護職が必要とされており、国をあげて介護職の担い手を増やすべく、“介護職員処遇改善加算”の改定や月額賃金の改善などの施策が打ち出されています。
また、職員向けに資格取得支援を行う事業所も増えています。
具体的には、受講費用の補助や研修中の給与支給、資格取得後の手当支給といった内容で、介護職のスキルアップや定着を図ることを目的としたものです。
参照:
厚生労働省「介護保険制度をめぐる最近の動向について」、介護人材の処遇改善等(改定の方向性)
介護職の3つの活躍フィールド
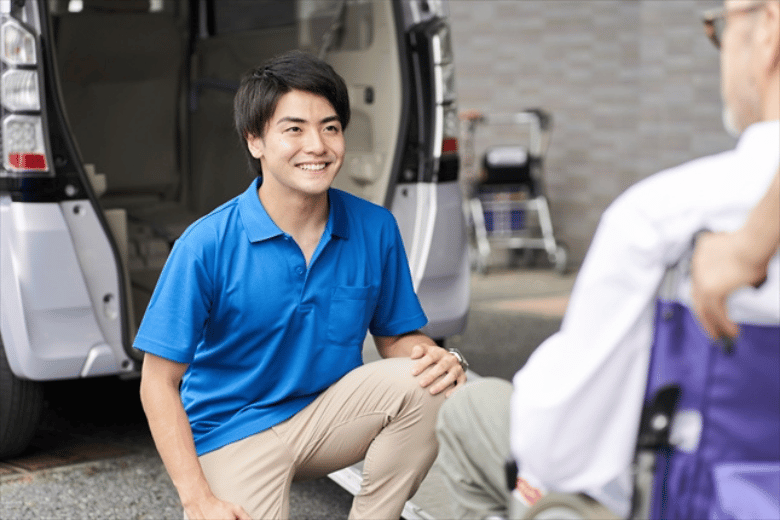
ここからは、介護職の活躍するフィールドを3つに分けて紹介します。
①居宅サービス
居宅サービスは、自宅で生活する要介護者向けの介護保険サービスです。ここでいう“居宅”には自宅のほか、有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅など、高齢者向けの住まいも含まれます。
主な居宅サービスは、訪問介護(ホームヘルプサービス)、訪問入浴、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導など「介護・医療等の専門職が自宅(居宅)を訪問して提供するサービス」と、デイサービス(通所介護)、ショートステイ(短期入所サービス)など「自宅(居宅)から通いで訪れる人向けに提供するサービス」に分けられます。
「介護が必要になっても自宅で暮らし続けたい」という要介護者が安心・快適に、またできる限り自立した生活を送れるようサポートします。
②施設サービス
施設サービスは、自宅で暮らすことがむずかしい人のための入所型サービスで、中・長期間にわたり施設で過ごす高齢者向けに、介護ケアを提供します。
主なサービスは次の4つです。
● 介護老人保健施設
● 介護療養型医療施設
● 介護医療院
どこに入所するかは、要介護者の介護度や必要とする医療的ケア、生活背景、利用目的によります。
上記のうち特別養護老人ホームは公的施設で、利用者は安価で入所できるうえ、充実した介護サービスが受けられます。近年は医療的ケアを行うところや看取りに対応するところも多く、入所待ちの高齢者が全国で数十万名にものぼるとされています。
年齢を重ねると身体の不調やできないことは増え、自宅で暮らせなくなる人も少なくありません。その受け皿である施設サービスは、超高齢社会にとって欠かせない存在です。
③地域密着型介護サービス
地域密着型介護サービスは、2006年の介護保険制度改正により創設された制度で、「中重度の要介護者や認知症をもつ人が無理なく在宅生活を継続できるようにすること」を目的としています。
主なサービスは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型デイサービス(認知症対応型通所介護)、グループホームなど。
地域密着型介護サービスの特徴は、事業所の規模が小さい点です。
運営事業者の管理は市区町村が担い、サービスの利用対象はその地域に暮らす人に限定されます。地域や利用者との距離が近いことで、地域特性や一人ひとりのニーズにあったケアを提供できると期待されています。
参照:
厚生労働省「地域密着型サービスについて」、厚生労働省「介護保険の解説 -サービス編 -」
介護職の平均年収・平均月給

介護職の年収や月給は、他の職業と同様に勤続年数や資格の有無により変動します。
ここからは厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」をもとに、さまざまな条件ごとの平均給与をみていきましょう。
■勤続年数別
| 勤続年数 | 平均月給 | 平均年収 |
| 1年 | 29.8万円 | 355万円 |
| 5年 | 33.1万円 | 397万円 |
| 10年 | 33.7万円 | 404万円 |
| 15年 | 35.9万円 | 430万円 |
| 20年以上 | 38.2万円 | 459万円 |
■年齢別(男性)
| 年齢 | 平均月給 | 平均年収 |
| 29歳以下 | 31.6万円 | 379万円 |
| 30~39歳 | 35.6万円 | 427万円 |
| 40~49歳 | 37.7万円 | 452万円 |
| 50~59歳 | 36.1万円 | 434万円 |
| 60歳以上 | 30.7万円 | 368万円 |
■年齢別(女性)
| 年齢 | 平均月給 | 平均年収 |
| 29歳以下 | 30.5万円 | 366万円 |
| 30~39歳 | 32.8万円 | 393万円 |
| 40~49歳 | 33.6万円 | 404万円 |
| 50~59歳 | 33.8万円 | 405万円 |
| 60歳以上 | 31.7万円 | 372万円 |
■勤続年数別の賞与平均値
| 勤続年数 | 平均支給額 |
| 1年未満 | 5.5万円 |
| 1~4年 | 38.5万円 |
| 5~9年 | 49.8万円 |
| 10~14年 | 57.0万円 |
| 15年以上 | 64.9万円 |
介護職としての実務経験が3年以上あると、国家資格である“介護福祉士”の受験資格が得られます。勤続5年目に給与が大幅に上がるのには、勤続3年~5年の間に介護福祉士の有資格者が増えることが影響しています。
また、勤続20年以上の介護職のなかには役職に就いたり、施設長になったりする人もおり、昇進・昇格により給与が上がると考えられます。
年齢別の平均給与をみると、年代ごとに大きな差はありません。介護職は他の職種と比べ、年齢を重ねても活躍し続けられる仕事といえるでしょう。
参照:厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」
出典:政府統計の総合窓口e-Stat「賃金構造基本統計調査 / 令和6年賃金構造基本統計調査 一般労働者 職種」
介護職の平均年収
国税庁の「令和5年分 民間給与実態統計調査」によると、医療・福祉業界の平均年収は404万円で、全職種の平均年収460万円と比較すると、約55万円低いことがわかります。
なお、平均年収にはアルバイトや派遣社員といった非常勤で働く人の給与も含まれます。それを念頭に置き、あくまで参考程度に捉えておきましょう。
参照元:
国税庁「令和5年分 民間給与実態統計調査」、厚生労働省「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」
介護職の平均月給
厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」をもとに、介護職の平均月給についてみていきましょう。
| 勤務形態 | 基本給 | 平均給与 |
| 常勤 | 19.2万円 | 33.8万円 |
| 非常勤 | 12.9万円 | 19.6万円 |
平均給与額には基本給のほか、資格手当や職務手当といった各種手当、処遇改善一時金などを含みます。
介護職のボーナス(平均賞与)
厚生労働省の調査「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」によると、2024年度の介護職(医療・福祉施設等)の平均賞与額は50.8万円でした。
同じく厚生労働省の「毎月勤労統計調査」によると、全職種の平均賞与額は82.7万円。すべての職種の平均賞与と比べると、介護職の賞与は32万円ほど下回ります。
介護職の賞与も他の職業と同様に、勤続年数や資格の有無が大きく影響します。
さらに介護職の場合は就業先によっても支給額に差が生じます。
とくに医療法人や社会福祉法人が運営する事業所は3~4ヶ月分の賞与が支給されるところが多く、民間の企業が運営する事業所と比べると、賞与額が高い傾向にあります。
参照:
厚生労働省「令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況」、厚生労働省「毎月勤労統計調査(全国調査・地方調査):結果の概要」
介護職の初任給(平均月給)
社会人(既卒者)の採用を中心とする法人・事業所が多いこともあり、新卒介護職の初任給に関する公的なデータはありません。
厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」によると、勤続1年の介護職の平均月給は約29万円で、夜勤手当がつく分、他の職種と比べ、高いことがわかります。税金・健康保険・厚生年金などを差し引いた手取り額は約23~24万円です。
また、介護福祉士・実務者研修・初任者研修といった資格を持つ人と無資格者とでは、初任給に差が出ます。
【施設形態別】介護職の平均年収・月給・時給
介護職には“交替勤務”“日勤のみ”“夜勤のみ”とさまざまな働き方があります。
夜勤をするとその分の手当が支給されるため、入所型の事業所や病院など、夜勤のある職場は平均給与が高くなります。
厚生労働省の「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」をもとに、施設形態ごとの平均給与をみていきましょう。
| 施設形態 | 平均年収 | 平均月給 | 平均時給(※) |
| 特別養護老人ホーム | 417万円 | 36.1万円 | 1,407円 |
| 介護老人保健施設 | 406万円 | 35.2万円 | 1,380円 |
| 訪問介護 | 378万円 | 34.9万円 | 1,728円 |
| デイサービス | 330万円 | 29.4万円 | 1,261円 |
| 有料老人ホーム | 376万円 | 36.1万円 | 1,492円 |
| グループホーム | 349万円 | 30.2万円 | 1,327円 |
※時給には派遣社員・登録ヘルパーの給与を含む
【資格別】介護職の平均年収・月給・時給
資格の有無や種類によっても、介護職の給与は大きく変動します。
なかでも国家資格である介護福祉士と無資格者の月給には、約6万円の差があります。
| 資格 | 年収 | 月給 | 時給(※) |
| 介護福祉士 | 397万円 | 35.0万円 | 1,612円 |
| 実務者研修 | 362万円 | 32.7万円 | 1,553円 |
| 初任者研修 | 360万円 | 32.4万円 | 1,579円 |
| 保有資格なし | 322万円 | 29.0万円 | 1,330円 |
※時給には派遣社員・登録ヘルパーの給与を含む
【都道府県別】介護職の平均年収・月給・時給
地域の物価、運営法人の経済力は、給与額に大きな影響を与えます。
とくに人口や要介護者が多いエリアは、介護職のニーズが高く、引く手あまたです。そのため近隣の競合施設との差別化を図るべく、高給与を提示する法人・事業所が多い傾向にあります。
東京都・神奈川県・埼玉県などの首都圏、愛知県・大阪府といった主要都市の平均給与が高いのには、そうした背景もあるのです。
介護職の平均年収が高い都道府県ベスト5
厚生労働省の「賃金構造基本統計調査」をもとに、都道府県ごとの介護職の平均年収について、上位順にみてみましょう。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
| 1位 | 神奈川県 | 440万円 |
| 2位 | 東京都 | 434万円 |
| 3位 | 石川県 | 404万円 |
| 4位 | 静岡県 | 398万円 |
| 5位 | 福井県 | 394万円 |
1位・2位の神奈川県・東京都は物価が高いこと、また競合事業所との差別化を図るために、地域手当を増額する法人が多いことが高年収の一因です。
また3位の石川県については、2024年元日に起きた震災(令和6年能登半島地震)を受け、被災地支援の一環として行った「石川県被災地介護・福祉人材確保支援事業」により、同年度の介護職の平均年収が上がったと考えられます。
上位5位にかかわらず、各都道府県が介護人材の確保や定着のために、独自の施策を進めています。年収には地域ごとの物価や運営法人の対策以外に、自治体の取り組みも影響しているのです。
参照:
令和6年賃金構造基本統計調査 結果の概況
石川県被災地介護・福祉人材確保支援事業
介護職の平均年収が低い都道府県ワースト5
介護職の平均年収が低い都道府県も、あわせてみていきましょう。
| 順位 | 都道府県 | 平均年収 |
| 1位 | 鹿児島県 | 327万円 |
| 2位 | 宮崎県 | 329万円 |
| 3位 | 長崎県 | 331万円 |
| 4位 | 高知県 | 335万円 |
| 5位 | 秋田県 | 336万円 |
これらの県は共通して比較的物価が低く、地域手当の額も少ない傾向にあります。また九州地方では、非正規雇用として働く人が多いことも、平均収入の低さに影響しています。
平均年収は調査する年によって変動します。順位は参考程度にみておくとよいでしょう。
介護職が年収を上げる5つの方法

ここからは、介護職が年収アップを図る方法について、解説していきます。
① 介護福祉士など上位の資格を取得する
介護福祉士やケアマネジャーの資格を持っていると、基本給が上がったり、資格手当が支給されたりし、給与がアップします。在職中に新たに資格を取得した場合も、人事部門に申告することで資格手当が支給されるでしょう。
とくに介護福祉士やケアマネジャーは、介護系の資格のなかでも上位資格に該当します。
国家資格である介護福祉士を取得するには、実務経験をはじめとした資格要件をクリアし、試験に合格する必要があります。
ケアマネジャーは各都道府県が認定する公的資格で、介護福祉士・看護師といった国家資格を持つ人、一定期間、相談支援業務に従事した人にしか受験資格が与えられません。そのため資格取得のハードルは高いといえます。
介護福祉士やケアマネジャーには高い専門性が求められる分、給与も高くなるのです。
② 夜勤の勤務回数を増やす
施設形態別の平均収入の表で紹介したとおり、特別養護老人ホームや介護老人保健施設で働く介護職の平均年収は、他の施設形態に比べ高い傾向にあります。その一番の理由は、夜勤があることです。
就業する事業所や地域、保有資格によって差があるものの、夜勤手当の相場は1回あたり3,000~10,000円です。体力に自信がある人にとっては、夜勤の回数を増やすこと、夜勤のある職場へ転職することも、年収アップに有効な手段です。
夜勤回数を増やすことは、資格取得や昇格を目指すよりも行動に移しやすいでしょう。とはいえ夜間に働くことで、身体には負担がかかります。
自身の体力や健康状態と相談しながら、無理のない夜勤回数や働き方を見つけましょう。
③ 管理職ポジションへの昇進を目指す
管理職に就くと管理職手当が加算され、給与はアップします。また担当部署や施設全体で成果が出れば、賞与にも反映されるでしょう。
介護職の管理職ポジションは、“主任”“ユニットリーダー”“サービス提供責任者” “施設長”など。いずれも一定の実務経験や資格を持つ人が対象です。
“管理者候補”としての募集もあるため、転職を機にキャリアアップを目指すのもよいでしょう。
④ 給与水準が高い施設へ転職する
給与水準が高い事業所には、以下のような特徴があります。
● 処遇改善手当の支給がある
● 夜勤手当の金額が高い
● 賞与の支給額が高い
基本給や処遇改善手当・夜勤手当の金額は、法人・事業所の運営方針によるため、気になる求人を一つひとつチェックしていく必要があります。
賞与に関しては、民間企業が運営する事業所よりも、医療法人や社会福祉法人のほうが高い傾向にあります。とくに病院では医療職と同様の賞与額が支給されることが多いようです。
また、CMを放映しているような大手の民間企業は経営基盤が安定しており、給与・賞与ともに高めです。
⑤ 処遇改善加算が充実した事業所を選ぶ
介護事業所は、利用者に介護保険サービスを提供する対価として、国(厚生労働省)から“介護報酬”を受け取ります。国は一定の要件を満たしている事業所に対し、介護報酬額を上乗せして支払います。
このうち “処遇改善加算制度”は介護職の待遇に関わるもので、主な基準は以下のとおりです。
1,介護職にとって働きやすい環境を整えている
● 経験年数や保有資格にあわせた昇給制度がある
● 研修やキャリアアップの機会を制度として設けている
2,利用者に対し、質の高い介護ケアを提供している
● 法定基準よりも手厚い人員配置をしている
● 介護福祉士の割合が全介護職の30%を超えている
処遇改善加算の支給対象は介護職員に限定されており、同じ事業所で働いていても、ケアマネジャーや生活相談員、看護師ら他職種には支給されません。
介護職の資格の種類

多くの介護事業所では、無資格でも働くことができますが、一部の事業所では所定の資格がないと働けません。
資格を取得することで、介護の専門知識やスキルが身につき、利用者に対し、安全で質の高いケアが提供できるだけでなく、自身の給与アップやキャリアアップにもつながります。
①介護職員初任者研修(旧:ホームヘルパー2級)
介護関連の資格の中でも、最短で取得できる資格です。修了資格を得るには、研修と実習を含む計130時間の研修を受けたのち、かんたんな試験に合格する必要があります。
この資格を取ることで、身体介護・生活援助の基礎知識やスキルが身につきます。
②介護福祉士実務者研修
初任者研修の上位資格で、介護福祉士受験のためのステップともなる資格です。
研修時間は、初任者研修修了者で320時間、無資格者は450時間。うち50時間は医療的ケア(喀痰吸引・経管栄養)の実習です。この研修を修了することで、医療的ケアの必要な人を含め、多様な利用者の介護ケアができるようになります。
また、介護福祉士実務者研修を修了すると、訪問介護事業所では“サービス提供責任者”として働けます。
訪問介護計画書の作成、スタッフの育成やシフト管理、利用者・家族との連携など、現場業務だけでなく、事業所やサービスの管理・運営面に携われます。
③介護福祉士
介護福祉士は介護関連の資格の中で唯一の国家資格です。
実務経験を積み、国家試験に合格しなければならず、資格取得への道のりは長いものとなります。
一方で、資格を取得すると資格手当がつき、高収入を得られるようになります。くわえて転職先の選択肢が広がる、管理職への就任を目指せるなど、活躍の場も広がります。
④ケアマネジャー(介護支援専門相談員)
ケアマネジャーは、介護保険制度に関する専門知識を持つ専門職で、主な役割は要支援・要介護認定を受けた人のケアプラン作成です。
資格取得のハードルは高く、介護福祉士や看護師などの国家資格を持ち、保健・医療・福祉分野で実務経験が5年以上ある、または相談支援業務の実務経験が5年以上ある人でなければ、資格試験の前段階である“介護支援専門員実務研修受講試験”を受験できません。
資格取得までには時間も労力もかかるものの、ケアプラン作成や社会資源の紹介など、より広い視点で要介護者や家族とかかわれるようになります。
介護業界の将来性

介護職の需要は非常に高い反面、なり手はまだまだ足りていません。その解消に向けて、国(厚生労働省)は処遇改善施策を推進しています。
過去5年を振り返ると、まず2021年には“介護職員処遇改善臨時特例交付金”が新設されました。
この施策は介護職1名に対し、月額9,000円程度の交付金を支給するもので、2022年2月から9月までの期間限定で行われました。これをきっかけに「他産業と遜色ない賃金水準を目指す」ことを表明し、2024年2月には介護職1名あたり6,000円の賃上げを実現させました。
従来は介護事業所で働く介護職のみが対象の施策でしたが、2024年の施策では看護助手や訪問介護、障がい福祉系の事業所で働く介護職員にも対象が拡大されています。くわえて、パートで働く介護職も対象となり、労働時間に応じた給与アップが行われました。
「給与が低い」と思われがちな介護業界の仕事ですが、介護職は引く手あまたで、今後も待遇改善が期待できるでしょう。
スマイルナースについて
スマイルナースでは、医療・介護・福祉業界の看護師求人を掲載しています。スマイルナースに求人掲載を希望する病院や介護・福祉施設の多くは、介護人材も募っており、介護職の転職支援にも力を注いでいます。
介護職としての転職を考えている人は、ぜひご相談ください。医療・介護・福祉業界に精通したコーディネーターが転職をサポートします。
まとめ
超高齢社会を迎えた日本において、介護職は欠かせない存在です。一方で十分な給与が支給されていない実情があります。ただし国(厚生労働省)の処遇改善加算制度を中心に、介護職の処遇改善は着実に行われており、介護職の収入は今後も上がっていくでしょう。
記事で紹介した給与・キャリアアップの方法も、ぜひ参考にしてください。