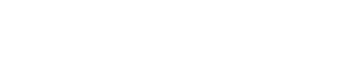看護師の中には「現在勤めている職場で、どれくらいの退職金をもらえるの?」「3年で辞めても退職金はもらえるの?」など退職金について疑問を感じる人もいるのではないでしょうか。退職金制度の詳細は、働く施設によって異なります。
そこで今回は、看護師が退職金を受け取れる時期や、職場ごとの相場を紹介します。
看護師の退職金はいつもらえる?
一般的に、退職金制度を設けている場合は、退職時に退職金が支給されます。実際の支給時期は、職場の雇用条件などによって異なります。ここでは一般的な退職金制度について紹介しますが、具体的な情報は所属する施設に確認しましょう。
退職一時金制度:退職時に支給
退職一時金制度は多くの企業で採用している制度です。厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査」によると、退職金制度を設けている医療・福祉業界の企業のうち、88.6%が退職一時金制度を採用しています。
出典:「平成30年就労条件総合調査 結果の概況」(厚生労働省)
退職一時金制度は労働協約や就業規則の退職金規定に準じて、退職時に一括で支給される制度です。支給額は働く施設によって異なりますが、勤続年数が長いと退職金の支給額も増える傾向にあります。
また、退職一時金制度で退職金を受け取ると退職所得控除の対象になります。そのため、勤続年数が長いほど控除できる金額は大きくなります。
企業年金制度(企業型DC):規定年齢から生涯・一定期間に支給
厚生労働省の「平成30年就労条件総合調査」によると、退職金制度を設けている医療・福祉業界の企業のうち、3.8%が企業年金制度を採用しています。退職一時金制度と併用している企業は、全体の96.2%です。
出典:「平成30年就労条件総合調査 結果の概況」(厚生労働省)
企業年金制度(企業型DC)とは、毎月施設(職場)が拠出(積み立て)して、従業員である看護師が自身で運用する制度のことです。自身の運用成績によって、退職金や年金の受け取れる額が変動します。
看護師は、掛け金をもとに資産配分などを決めて運用を行います。そして規定年齢(60歳)に達したときに年金資産の一時金、または年金形式で受け取ります。定年退職する場合には、年金資産の一時金を「退職金」という形で受け取ることになるのです。
ただし、掛け金は施設(職場)が負担してくれますが、退職金や年金などの年金資産は自身の運用次第になります。
前払い制度:現役時代に支給
一般的な退職金は看護師などの従業員が退職するタイミングに支給されますが、前払い制度は、退職金が賞与や給与に上乗せして支給される制度です。受取総額は、勤続年数や在職中の給与額に基づいて算定されます。
毎月の給与に上乗せしているため、月収は高くなります。一方で、前払い制度で支給される退職金は、給与所得として扱われるため、各種税金や社会保険料の負担が増えます。
【勤続年数別】看護師の退職金の相場
退職一時金制度を採用している施設の場合、勤続3年以上を支給対象にしているところが多いです。ここからは、その一例として、勤続年数別に支給される退職金の金額相場をご紹介します。
| 3年目 | 30万円程度 |
| 5年目 | 30〜50万円程度 |
| 10年目 | 250〜300万円程度 |
| 20年目 | 450〜600万円程度 |
| 30年目 | 800〜900万円程度 |
この表を見てもわかるように、勤続年数10年以上でぐんと支給額が上がります。
【職場別】看護師の退職金の相場
次に、定年退職時における退職金の金額相場をご紹介します。
| 国立病院 | 1,800~2,000万円程度 |
| 公立病院 | 都道府県立:平均1,400万円 政令指定都市:平均1,900万円 市町村立:平均1,800万円 |
| 私立病院 | 800〜2,000万円程度 |
国立病院や政令指定都市の公立病院では、高額の退職金が受け取れます。
【公務員】看護師の退職金の相場
ここからは、公務員の看護師の退職金について解説します。
国家公務員の場合
官公庁に勤める国家公務員の看護師の退職金は、国家公務員法によって定められています。
退職手当額=基本額(退職日の俸給月額×退職理由別・勤続年数別支給率)+調整額
参考として、内閣人事局の「退職手当の支給状況」によると、令和3年度中に退職した常勤職員の平均支給額は、定年退職で約2,100万円でした。
出典:「退職手当の支給状況」(内閣官房)
一般的な退職金に比べると、国家公務員の退職金はかなり高額であることがわかります。
地方公務員の場合
地方公務員の退職金は、地方公務員法によって国家公務員の制度に準じると定められています。
退職手当額=基本額+調整額
総務省の「令和4年地方公務員給与実態調査」によると、一般職における退職金の平均額は約1,210万円で、定年退職の場合は約2,150万円となっています。
出典:「令和4年地方公務員給与実態調査」(総務省)
地方公務員であっても、国家公務員とさほど変わりなく退職金が支給されることがわかります。
看護師の退職金の計算方法
公務員の場合、退職金の支給額は法律に則って決められますが、民間の医療機関はどのような計算で退職金の支給額を決めているのでしょうか。ここからは、基本的な看護師の退職金の計算方法を解説していきます。
基本給をもとにした場合
毎月支給される基本給に、勤続年数をかけて退職金を算定する方法です。
■計算方法
退職金=基本給×勤続年数
(例1)
基本給20万円で8年勤めた場合
20万円×8年=160万円
(例2)
1〜3年目の基本給が18万円、4〜6年目の基本給が19万円、7〜8年目の基本給が20万円で8年勤めた場合
(18万円×3年)+(19万円×3年)+(20万円×2年)
=54万円+57万円+40万円
=151万円
固定金(基本金額)をもとにした場合
役職や等級に応じて決められる固定金(基本金額)と勤続年数をベースに計算する方法です。
■計算方法
退職金=固定金×勤続年数
(例)固定額が15万円と定められており、9年間勤務した場合
15万円×9年=135万円
功績倍率をもとにした場合
基本給に勤続年数と功績倍率をかけて退職金を計算する方法です。
功績倍率は職場への貢献度によって決まり、1.0を基本値とします。高評価を得ると功績倍率は1.0以上になり、貢献度が低いと功績倍率は1.0未満になる場合もあります。
■計算方法
退職金=基本給×勤続年数×功績倍率
(例1)
基本給20万円で10年間勤務し、功績倍率が「1.4」であった場合
20万円×10年×1.4=280万円
(例2)
基本給20万円で10年間勤務し、功績倍率が「0.8」であった場合
20万円×10年×0.8=160万円
看護師が退職金を増やすには?
看護師が退職金を増やす方法には、以下の3つが挙げられます。
・役職につく
・資格を取得する
・転職する
基本給や功績倍率をもとに退職金を計算する職場の場合は、看護主任や看護師長、看護部長などの役職を目指すと良いでしょう。基本給がアップするため、その分退職金が増えます。
また、功績倍率をもとに退職金を計算する職場の場合は、資格を取得することで高評価を得やすくなります。認定看護師や専門看護師のほか、助産師や保健師、特定看護師(特定行為研修を受けた者)などの取得を目指すことがおすすめです。
そのほか、退職金の相場が高い職場へ転職することもひとつの手です。国立病院や公立病院、官公庁、公立の幼稚園・保育園、各自治体の保健所・保健センターなどが挙げられます。
まとめ
看護師の職場で採用されている退職金制度には、退職一時金制度、企業年金制度、前払い制度などがあります。
基本的には、勤続年数に応じて受け取れる退職金の額が増えますが、金額相場は職場によっても異なります。国立病院や公立病院で働く看護師や、国家公務員や地方公務員として働く看護師では、高額の退職金が受け取れる可能性が高いでしょう。
退職金の受取総額を増やすには、資格の取得や昇格を目指すといった方法のほか、退職金の相場が高い職場に転職する方法もあります。
看護師専門の転職エージェント「スマイルナース」では、国立病院や公立病院を含む求人を多数ご紹介しております。求職者の理想の転職を叶えるサポートをいたしますので、転職をご検討中の看護師は、ぜひ一度ご相談ください。