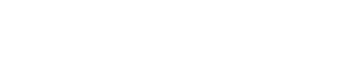看護におけるアドボカシーは、患者の権利擁護やニーズの代弁、質の高いケアを提供する上で不可欠な概念です。患者の声を尊重し、その人にとって最適な医療が提供されるよう、看護師がどのような役割を果たすべきかを、十分に理解することが求められます。
この記事では、アドボカシーの意味や重要視される背景、具体的な実践方法について詳しく解説します。
看護におけるアドボカシーの意味

アドボカシーとは、他者の権利や立場を擁護し、彼らが本来持つ権利を確保できるよう支援する行為を指します。
看護におけるアドボカシーとは、患者の権利擁護を指し、看護師が患者の価値観や希望を尊重し、最適な医療を受けられるよう支援する概念です。
看護師は患者の意思決定支援やプライバシーの保護を通じ、医療の質や安全の向上に寄与する役割も担います。これにより、患者が尊厳を保ちながら治療を受けられる環境を作り、医療チームとの信頼関係を構築します。
アドボカシーが重要視されている背景
アドボカシーが重要視されている背景には、患者の権利を守る必要性が高まった歴史的経緯があります。
アドボカシーという概念は、1970年代のアメリカで看護師の新しい役割として登場し、看護業界においても注目されるようになりました。当時、ケアリングが看護の基本概念とされていましたが、アドボカシーの概念が誕生したことで「看護師が専門性を発揮し、患者の声を代弁し権利を擁護することが、看護の重要な役割である」と認識されるようになったのです。
特に、医療において患者が意思決定を行う場面で、看護師がアドボケイト(代弁者)の役割を担うことは欠かせません。こうした流れを通じて患者の自律を尊重し、権利を守ることが、看護師の専門的役割として認識されています。
看護師が知っておきたい患者さんの権利
患者の権利を理解し擁護することは、看護師の重要な役割です。以下に、リスボン宣言(1981年に世界医師会(WMA)によって採択された「患者の権利に関する宣言」のこと)をもとにした患者の主要な権利を紹介します。
● 良質の医療を受ける権利
患者は、性別、年齢、社会的背景にかかわらず、差別なく適切な医療を受ける権利を持っています。医師は、患者の最善の利益を第一に考え、一般的な医学的原則に基づいた質の高い医療を提供する責務を負います。また、治療の選択肢が限られている場合でも、患者は公平な選定基準に基づいて治療を受ける権利が保障されるべきです。
● 選択の自由の権利
患者には、治療を受ける際に、担当医や病院、保健機関を自由に選択し、必要に応じて変更する権利があります。さらに、治療の各段階で、別の医師の意見を求め、セカンドオピニオンを受けることも認められています。これにより、患者は自身にとって最善の治療を選択するための情報と機会を得ることができます。
● 自己決定の権利
自己決定の権利は、患者が自らの健康に関し自由な決定を行うための基本的な権利です。医師は、患者が十分な情報を得た上で意思決定を行えるよう、検査や治療の目的、期待される結果、起こりうるリスクを適切に説明する必要があります。また判断能力のある成人患者は、診断や治療に対して同意または拒否する権利があり、情報の提供を受けた上で、自分の意思で治療を受けるかどうかを決定できるのです。
● 情報に対する権利
患者は、自身の診療記録や健康状態に関する情報提供を受ける権利を持ちます。この情報は患者が理解しやすい形式で提供されるべきであり、患者の文化的背景や理解力に配慮して提示される必要があります。また、第三者の情報が含まれていない限り、情報は患者に開示されるべきです。
● 守秘義務に対する権利
患者の個人情報や医療記録は厳格に守秘されなければなりません。医療提供者は、患者が明確な同意を示すか、法律に基づく場合を除き、その情報を第三者に開示してはなりません。患者の死後も守秘義務は継続され、情報は保護されるべきです。守秘義務を守ることで、患者と医療者の信頼関係が維持されます。
● 健康教育を受ける権利
患者は、個々の健康維持や疾病予防に役立つ情報を提供される権利を持っています。これには、病気の早期発見や健康的なライフスタイルを維持するための方法についての教育も含まれます。医療提供者には、患者が自分の健康に関する自己責任を果たせるよう、積極的な教育を行うことが求められます。
● 尊厳に対する権利
患者は、治療や医療教育の場で、その文化や価値観を尊重されながら、尊厳を持って扱われる権利を有します。痛みの緩和や人間的な終末期ケアを受けることも、この権利に含まれます。患者はできる限り快適で尊厳を保った状態で治療を受け、終末期には安らかな環境が提供されるべきです。
● 宗教的支援に対する権利
患者は、自身が信仰する宗教の聖職者による精神的・道徳的支援を受けるかどうかを選択する権利を持っています。
看護におけるアドボカシーのモデル別の概要
看護アドボカシーには、以下4つのモデルがあり、それぞれ異なる視点で患者支援のあるべきかたちを捉えています。
1. 人間尊重モデル
2. 実存的モデル
3. 機能的モデル
4. 文化間の橋渡し役モデル
看護アドボカシーを実践するうえで、各モデルの概要を理解することが重要です。
①人間尊重モデル
人間尊重モデルは、看護哲学者Lear Curtinによって提唱されたアドボカシーモデルです。このモデルの特徴は、以下の通りです。
● 道徳的わざとしての看護
看護は他者の福祉を向上させる「道徳的わざ」であるとされ、その哲学的基盤にアドボカシーを置いています。看護の知識やスキルは、善を求める道徳的行為に沿って磨かれるべきであり、看護師は患者のアドボケイト(代弁者)としての役割を担うことが理想とされています。
● 共通の人間性を基盤とする関係
看護アドボカシーは、看護師と患者が役割や立場を超えて同じ人間であるという共通の認識のもと人間性、ニーズ、人権を共有するという前提に基づいています。この共通認識のもとで、患者との関係を構築し、看護を提供することが求められます。
● 患者の人間性を尊重する視点
病気は患者の自律性や独立性を奪い、医療者への依存を強いるため、患者は自尊心や自己イメージが傷つきやすい状況に陥ります。人間尊重モデルは、看護師がこのような状況を理解し、患者の尊厳を守ることを重視しています。
参考:足立智孝|麗澤大学紀要第91巻 看護アドボカシー概念の検討
②実存的モデル
実存的モデルは、看護哲学者Sally Gadowによって提唱されたアドボカシーモデルです。このモデルの概要は以下の通りです。
● 自己決定の尊重
実存的モデルは、「自己決定の自由」を最も基本的かつ価値ある原則としています。患者本人が自らの意思で最終的な判断を行うことを重視し、看護者の役割はその意思決定を支援することです。これは、患者の利益を看護者が決定するのではなく、患者自身が行うことを基本としています。
● 真の意思決定の支援
患者の意思決定が「本当」または「真実」のものであるよう支援することが看護者の重要な役割です。これは、患者が自分の価値観や置かれた状況を総合的に考慮し、自分にとって最も価値があると信じる選択を行えるようにすることを意味します。
● 意思決定のプロセス
看護者は、患者が自身の価値を見つけ出し、それに基づいて意思決定を行うことを助けます。これにより、患者の意思決定が他者の影響を受けず、完全に自身の意思に基づいたものとなるように支援します。
このモデルでは、看護者は患者に寄り添い、意思決定の過程で支援者としての役割を果たし、患者が自分の価値に基づく選択をするための支えとなります。
参考:足立智孝|麗澤大学紀要第91巻 看護アドボカシー概念の検討
③機能的モデル
機能的モデルは、看護教育者Mary F. Kohnkeによって提唱されたアドボカシーモデルです。このモデルの特徴は以下の通りです。
● 自己決定権の尊重
機能的モデルは、患者には自己決定権があるという確信に基づいています。看護師は、患者に必要な情報を提供し、自己決定を支援する役割を担います。これにより、患者は適切な選択を行えるようになります。
● 客観的な関わり
Gadowの実存的モデルが看護師と患者の深い関わりを強調するのに対し、機能的モデルは看護師が客観的に患者をサポートすることを求めています。看護師は患者が下した決定を尊重し、擁護する役割にとどまり、個人的価値の探求までは求められません。
● 偏見のない情報提供
看護師は患者に対して、公平で偏りのない情報を提供することが求められます。これにより、患者が十分な情報に基づいて意思決定を行えるよう支援します。偏見のない態度は、患者のニーズに客観的に対応し、信頼関係を築くために重要です。
機能的モデルは、実践における具体的行動を示し、看護師がアドボカシーを安全かつ効果的に遂行するための枠組みを提供します。
参考:足立智孝|麗澤大学紀要第91巻 看護アドボカシー概念の検討
④文化間の橋渡し役モデル
文化間の橋渡し役モデルは、Jezewskiによって提唱され、看護師が患者アドボカシーにおいて「調停者」としての役割を果たすことを示しています。このモデルの概要は以下の通りです。
● 調停役としての看護師
看護師は、患者の日常の文化システムと医療供給システムの間に存在する文化的な差異を埋める役割を担います。患者が医療システムに直面する際に生じるカルチャーショックを軽減するため、看護師が仲介役として説明や支援を行うことが重要です。
● 文化の広い定義
Jezewskiは、「文化」を広義に、認識、行動、言語などの基準システムと定義しています。患者はヘルスケアシステムという異文化に入る際、自分の持つ価値観や行動と異なるものに直面し、不安を抱えることが多いものです。看護師は、この違いを理解し、患者がスムーズに医療を受けられるようにサポートします。
● エンパワーメントとシステム変革
Kosikは、看護師が患者の権利を守り、医療システムがそれを妨げないよう行動することが文化的仲立ちの要だと述べています。看護師は患者をエンパワーし、政治的・社会的な障害を取り除くことに努めるべきです。
このモデルでは、看護師が患者の立場を理解し、文化的背景を考慮した上で支援することで、医療の質を高めることが期待されています。
参考:竹村節子|医療における患者アドボカシ一 看護師の役割に影響を与える要因の検討一
看護アドボカシーのモデル理解から実践へ
看護アドボカシーには、患者を支えるための多様な視点が存在し、4つのモデルで表現されます。
「人間尊重モデル」では患者の尊厳と福祉を中心に据え、看護師が道徳的支援者として患者と関わります。「実存的モデル」は患者の自己決定を重視し、看護師がその意思決定をサポートする姿勢を示しています。
「機能的モデル」は、情報提供や支援を通じて患者が適切な判断をできる環境を整えることに焦点を当て、「文化間の橋渡し役モデル」では、異なる文化的背景を持つ患者と医療システムの間で調停役として働くことを強調します。
これらのモデルの理解は、患者に寄り添い看護アドボカシーを実践するための重要な指針となるでしょう。
看護現場でアドボカシーを実践する方法

看護師がアドボカシーを実践するためには、患者の権利を守り、必要な情報を提供し、意思決定を支援することが重要です。
ここからは、具体的な方法として、どのようにこれらを実現していくかを見ていきましょう。
必要な情報を提供する
看護現場において、アドボカシーを実践する上での重要な要素は、患者やその家族に必要な情報を提供し、治療への理解を深めることです。
医療の現場では、患者が医学的な情報を十分に理解できないまま治療が進められるケースも少なくありません。情報が不足した状態では、患者は治療に対して不安を感じやすくなり、誤解や誤った選択をするリスクが高まります。
また、情報不足によって患者の理解が不十分なまま治療が進むと、治療結果への不満や、患者-医療者間の信頼関係の損失につながる可能性もあるでしょう。
看護師は、患者や家族が納得して意思決定できるよう、必要な情報を分かりやすく伝えることが大切です。適切な情報提供と支援を通じて、看護師は患者の健康と安心を守る役割を果たします。
権利を尊重する
看護アドボカシーにおいて、患者の権利や意思決定を尊重することは重要です。
患者が自身で治療方針を決定できない場合、看護師は患者の家族や周囲の人たちと連携し、本人に負担をかけない最善の方法を模索する役割を果たします。
また、看護師には患者の代弁者として、その価値観や信念に基づいた決定ができるよう支援し、尊厳やプライバシーを守ることが求められます。
すべての人々は、背景や状況に関わらず、最高水準の健康を享受する権利があります。看護職は、この権利を守り、高い倫理観をもって行動し、人間の生命と尊厳を尊重しながら、患者がその人らしい健康な生活を送れるよう尽力します。
参考:日本看護協会|臨床倫理のアプローチ
参考:日本看護協会|患者・家族との信頼関係と倫理
意思決定を支援する
看護アドボカシーにおいて看護師は、患者の意思決定を支援する役割を担います。特に患者が急な生命の危機に陥り、意思表示が難しい場合、医療者との意思疎通が困難となり、家族が代理として重要な決定を行うことが求められます。
看護師は、患者の意思を尊重し、家族が適切な決定を行えるようにサポートし、不安や葛藤を和らげます。
高齢者や子どもの場合、意思決定能力が不十分なこともあり、看護師はその特性を理解し、患者の意向をできる限り反映できるよう支援します。
家族や患者が納得のいく選択ができるよう、倫理的な視点を持って意思決定プロセスを見守ることが、看護アドボカシーにおける役割なのです。
参考:日本看護協会|意思決定支援と倫理(1)代理意思決定の支援
参考:日本看護協会|意思決定支援と倫理(2)高齢者の意思決定支援
参考:日本看護協会|意思決定支援と倫理(3)子どもの意思決定支援
セルフマネジメントを行えるよう援助する
看護アドボカシーにおいて、患者が自身の健康状態を把握し、治療に積極的に関わること、つまり「セルフマネジメント」を行えるように支援することが重要です。
看護師は従来の「看護師主導の援助」から、患者が主体的に取り組む「患者主体のセルフマネジメント」へとシフトする役割を果たします。
具体的には、患者が必要な知識やスキルを習得し、自ら問題解決に取り組めるよう情報提供や教育を行います。さらに、患者が目標を設定し、自身の行動に責任を持つ「セルフマネジメント」の力を引き出します。
看護師は患者の疑問や不安に共感し、信頼関係を築くことで治療に対する意欲を高めるサポートを提供します。これにより、患者は自らの健康管理に自信を持ち、より良い治療結果を目指せるようになるでしょう。
信頼関係を築く役割を担う
患者の意志を把握し、適切な医療を提供するために、看護師は、日頃から患者と信頼関係を築くことが重要です。
看護師が患者に積極的に声をかけ、対話を重ねることで、患者は不安や疑問を率直に伝えやすくなります。他の医療スタッフには言い出せないような悩みも、看護師が耳を傾け受け止めることで、患者は「自分の気持ちが尊重された」という安心感を抱き、安定した治療環境が整います。
看護アドボカシーの実践には、信頼を基盤としたコミュニケーションが不可欠です。患者や家族との信頼関係を築くことは、看護提供の前提であり、協力を引き出すことで、質の高い医療や福祉サービスの実現に繋がります。
看護師には日常の関わりの中で患者と信頼関係を構築し、患者の意志を尊重した看護を提供することが求められます。
専門家ごとに異なる意見の調整をする
看護アドボカシーにおいて看護師は、患者を中心に据え、多職種間の意見を調整する役割を担います。
家族や医療福祉の専門職ら患者を取り巻く人たちはそれぞれ異なる視点や価値観を持ち、意見が対立することもあります。看護師はそのような場面で、異なる立場の意見を理解し、患者にとっての最善を見据えて調整役を担います。看護師が主体となって意見の相違を整理し、それぞれの価値観の違いを尊重しながらチームで解決策を検討できるよう調整を行うのです。
看護師は、患者とその家族の希望をチームに共有し、チーム全員で共通の認識を持つよう働きかけ、最良のケアを提供します。専門家間の調整には、看護職が持つ倫理観とコミュニケーション力を活かし、組織としての解決策を導く役割を果たすことが必要です。
参考:日本看護協会|多職種連携と倫理
参考:日本看護協会|臨床倫理のアプローチ
看護におけるアドボカシーの注意点

看護においてアドボカシーを実践する際には、いくつかの注意点があります。
まず、アドボカシーは解釈によって行為の幅が広がります。そのため、混乱を招くことがあることに注意が必要です。看護師が患者の権利を擁護する際、組織やシステムと対立する可能性もでてくるのです。
たとえば、医師の説明不足や組織の方針によって患者の権利が侵害される状況では、看護師は組織内で孤立するリスクを抱えながらも、アドボカシーの実践を求められることがあります。
また、看護師が個人的にアドボカシーを行うことで、他の医療者との連携が不十分となり、アドボカシーが看護師独自の価値観の押しつけと見なされる危険もあります。
アドボカシーの実践においては、看護師個人ではなく医療チーム全体で患者の権利を守る協力体制をつくる必要があります。メンバーそれぞれが助け合う「協力」と、全員が役割を果たしあいながら共通の目標に向かっていく「協働」の違いを理解し、互いの専門性を尊重しながら共通の目標に向かうことで、看護アドボカシーは真の意味で効果を発揮します。
看護師の役割は、患者を支える医療者全体の一専門職として協働することです。
アドボカシー以外の重要な概念
看護においては、アドボカシー以外にも重要な倫理的概念として「責務」「協力」「ケアリング」があります。これらは看護職が倫理的な意思決定を行う際の基盤となり、行動の指針を提供します。
①看護実践の責務
看護実践の責務には、法的責務と道徳的責務があります。
法的責務は、「保健師助産師看護師法(保助看法)」などの法律に基づき、看護師としての業務や義務が明確に規定されています。
一方、道徳的責務は、日本看護協会の「看護職の倫理綱領」(2003年)や「看護業務基準(2021年改訂版)」などで示されており、看護職が持つ倫理観に基づいて行動することを求めています。これには患者の安全や権利の擁護、尊厳の尊重が含まれ、日々の看護実践において重要な指針となっています。
さらに、国際看護師協会(ICN)が掲げる「看護師の倫理綱領」(2012年)でも、看護師の基本的責任として「健康の増進、疾病の予防、健康の回復、苦痛の緩和」が強調されています。
この責務では、「単なる業務遂行を超えて、患者に最善のケアを提供する」という意識的な責任を持つことを求められます。
看護職は、これらの基準に基づき、自らの行動が患者に対してどのような影響を与えるのかを常に考慮し、責務を果たす必要があります。
②ケアリング
ケアリングとは、看護職の援助行動において重要な概念です。
具体的には、①対象者との相互的な関係性を築くこと、②対象者の尊厳を守り大切にしようとする看護職の理想や倫理的態度、③気づかいや配慮が行動に反映され、対象者に伝わることで成り立ちます。
これにより、対象者は安らかさや癒しを感じ、自らを振り返るきっかけや成長、危険の回避、健康の改善といった前向きな効果を見出すことができます。
ケアリングは、ただの行為ではなく、ケアされる人とケアする人の双方に人間的成長をもたらすことが重視される理念です。
看護職にとってケアリングは、単なる技術や知識以上に、患者に寄り添い尊重し続けることで患者のQOL(生活の質)向上に貢献する、看護の本質といえるでしょう。
まとめ
看護アドボカシーは、患者の権利とニーズを擁護し、最適なケアを提供するために看護師が果たす重要な役割です。
患者中心のケアを実現するには、情報提供、意思決定支援、権利の尊重などの実践が求められます。しかし、看護師が安心して働ける環境があってこそ、これらが実現します。
スマイルナースでは、70,000件を超える豊富な求人を取り扱っています。会員登録後のサポートも充実しており、専任のコーディネーターが個々のスキルやキャリアプランに合わせた職場を提案します。
「アドボカシーを実践できる職場を見つけたい」「自分の価値観に合った職場環境で看護の質を高めたい」と考える看護師は、ぜひスマイルナースを活用ください。