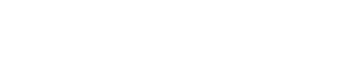看護師の日々の業務の中で欠かせない環境整備。しかし、その重要性と効果的な方法について再確認する機会は意外と少ないのではないでしょうか。就業先や看護師ごとによりやり方が異なることもよくあります。
この記事では、環境整備の目的と手順、効果的な看護計画の立て方について詳しく解説します。環境整備への理解を深め、より質の高いケアを提供できる看護師を目指しましょう。
看護における環境整備の目的

環境整備は、患者の療養生活を支えるために大切な看護ケアのひとつです。看護における環境整備の目的は、大きく5つあります。
● 安全な環境をつくる
● 清潔な環境をつくる
● 快適な療養環境をつくる
● コミュニケーションのきっかけをつくる
● 業務が安全かつスムーズに行える環境を整える
詳しく解説します。
安全な環境をつくる
患者の周りの環境を安全に整えることは、環境整備を行う最大の目的です。
入院中、患者の生活や行動範囲はベッド周りに限定されます。環境整備が行き届いていないと、思わぬ事故につながることがあります。
立位や歩行が不安定であったり、認知症やせん妄で行動が予測できなかったりと、患者のADLや自立度はさまざまです。転倒やベッドからの転落がないよう、ひとりひとりの自立度に合わせた環境を整えましょう。たとえば、「つまずきそうな段差や障害物がないか」「寝ているうちに落ちないようにベッド柵が配置されているか」など、患者のとる行動を予想しながらベッドの周囲を見直すとよいでしょう。
清潔な環境をつくる
病室を清潔に保つことも、環境整備の目的のひとつです。
入院中の患者のなかには、健康な人に比べ免疫力が低下している人も多くいます。また、病院にはさまざまな感染症の患者が集まっています。感染症をまん延させないためにも、衛生管理を徹底する必要があるのです。病室の清潔を維持する取り組みは以下のとおりです。
● 換気をして新鮮な空気を取り入れる
● よく触れる場所を消毒する
● シーツやリネンを清潔に保つ など
生活空間を清潔に保つことは、感染予防に役立つだけでなく、患者が快適に過ごせる環境を整えることにもつながります。
快適な療養環境をつくる
快適な療養環境をつくることも大切です。温度や湿度・明るさ・清潔さなど、生活空間の快適さは患者のストレスを軽減し、心身のリラックスを促します。また、居心地のよい空間は気分を前向きにし、回復やリハビリへの意欲を高めることにもなります。たとえば、次のことに注意して療養環境を整えましょう。
● 室温・湿度は快適かどうか
● 換気ができているか
● 不快なにおいはないか
● カーテンによりプライバシーへの配慮がなされているか
● 同室患者との関係で困っている様子はないか
患者が心地よい入院生活を送れるように配慮することも、環境整備の重要な目的です。
コミュニケーションのきっかけをつくる
環境整備は、患者とのコミュニケーションのきっかけづくりにも役立ちます。たとえば窓を開けながら「今日は良い天気ですね」と話しかけたり、ベッドメイキングをしながら「昨晩はよく眠れましたか」と声をかけたりすることで、自然な会話が生まれます。このような何気ない会話をきっかけに、患者の興味関心や困りごとを聞き出したり、信頼関係を築いたりできるものなのです。
また、患者との会話から、下記のように今後の援助にいかせる情報が得られることもあるでしょう。
● 治療への不安
● 退院後の生活に対する悩み
● 自宅環境
● 家族との関係性や協力者の有無 など
患者とのコミュニケーションを深めることは、より個を大切にした看護ケアの実践につながります。
業務が安全かつスムーズに行える環境を整える
環境整備の主目的は「患者が安全・快適に過ごせること」ですが、それは同時に医療スタッフが安全かつスムーズに働ける環境を整えることでもあります。
たとえば看護師が患者の移動支援や移乗をする際、周囲に障害物があれば、患者本人・看護師の双方に危険が及ぶ可能性が高まります。また、感染症は患者だけでなく、医師や看護師らスタッフにも感染するリスクがあります。病室の清潔を保つことは、病院全体の安全性を高める要素となるのです。加えてスタッフが安全に、継続的に働ける環境が、結果的に患者へのよりよいケアにつながるといえるでしょう。
看護における環境整備の流れと注意点

ここからは、看護における環境整備の流れやそれぞれの方法、注意点について紹介します。
なお、この手順は一般的なものです。ルートが閉塞している、モニターのアラームが鳴っているなど、すぐに対応すべき事柄がある場合には、緊急度の高いものから実施しましょう。
| 手順 | 方法と注意点 |
| 1. 準備 | 必要な物品(消毒用クロス・ゴミ袋・手袋など)をそろえる 患者に環境整備を行うことの説明と同意を得る |
| 2. 換気 | 患者のプライバシーに配慮する 患者に直接風が当たらないよう注意する |
| 3. ベッド周りの整理 | シーツのしわを伸ばし、褥瘡予防に努める ベッド柵やナースコールの位置を確認する |
| 4. 廃棄物の処理 | 尿器やポータブルトイレを設置している場合は確認し、適切に処理する 感染予防を意識する |
| 5. 清掃・消毒 | ベッド柵やテーブルなどを消毒用クロスで念入りに拭く 清潔な場所から汚染場所へと一方向に拭く |
| 6. 物品の配置 | 患者のADLに合わせて、本人に確認しながら身のまわりの物を配置する よく使うものは手の届く位置に設置する |
| 7. 環境調整 | 室温・湿度・照明を適切に調整する 騒音や不快なにおいがないか確認する |
| 8. 安全確認 | 転倒リスクがないかどうか確認する 医療機器やルート類の配置を整理する |
| 9. 終了 | 患者に環境整備の終了を伝え、他に要望がないかを確認する 手指消毒を行う |
実際の環境整備の場面では、患者の年齢や認知機能、ADLの状況に合わせてベッド周囲を整えていきます。たとえば高齢者の場合、筋力や認知機能の低下により、転倒リスクが高くなります。物品の配置だけでなく、患者が滑りやすい靴や裾の長い服を身に着けていないかなどを観察・予測して、安全に配慮する必要があるのです。
このように、ひとりひとりにとって最適な環境を整備するためには、きめ細かな配慮と観察力が求められます。環境整備の基本的な手順や方法、注意点を把握したうえで、個々の患者に合わせた対応を心がけていきましょう。
環境整備の看護計画を立てる方法

環境整備は看護師の基本的な技術のひとつです。とはいえ、対象となる患者の年齢や疾患、生活習慣などを踏まえ、ひとりひとりに合った計画を立てる必要があるため、むずかしく感じることもあるでしょう。実際に、留意点を意識しながら手順どおりに行ったとしても、患者のADLに適した環境になっていなければ、問題が生じることもありえます。
ここからは、より効果的な環境整備を行うための看護計画の立て方について解説します。
看護目標を設定する
環境整備では、患者が安全に、安楽に過ごせるような空間をつくることです。また、看護師にとっても患者とのコミュニケーションの機会を増やすきっかけになります。看護目標はこれらに留意して設定するとよいでしょう。
たとえば次のような看護目標が挙げられます。
● 転倒・転落を未然に防止できる
● 患者が心地よく、安楽に過ごせる
● 病室の清潔を維持し感染症を防げる
● 看護師とのコミュニケーションにより患者の意欲が向上する
患者の病状や年齢、ADL状況などを考慮し、個別性のある看護目標を立案しましょう。
必要な観察項目を挙げる
環境整備を効果的に行うためには、適切な観察項目を設定する必要があります。観察項目の例を紹介します。
<清潔管理>
● シーツ・寝衣・ベッド周囲の汚れ
● ベッド上や周囲のゴミの有無
● 尿器やポータブルトイレに排泄物がないか
<安全の確保>
● コード類・点滴・酸素チューブの整理状況
● ベッドの高さと柵の固定状態
● 床が濡れていないか
● 履物は適切か
● 車椅子やポータブルトイレの位置は適切か
● 医療機器の動作状況
● 医療機器の配置場所
<環境>
● 室温と湿度
● 騒音レベル
● 部屋の明るさ
● においの有無
<プライバシーの保護>
● カーテンやドアの適切な開閉
● 同室患者との関係性
設定した観察項目をもとに日々観察し、記録に残していきます。これにより、担当看護師が交代しても、目標に向かって一貫した環境整備を継続できるのです。
また観察項目は、患者の状態の変化に応じて柔軟に見直す必要があります。継続的な観察と記録、見直しを繰り返し行い、より効果的な環境整備の実現につなげましょう。
まとめ
この記事では、環境整備の目的と手順、効果的な看護計画の立て方について解説しました。環境整備は患者の安全と安楽を守り、質の高い看護ケアを提供するために重要な業務のひとつです。効果的な環境整備を行うためには、その目的を理解し患者の個別性を考慮した看護計画を立案することが大切です。
環境整備を効果的に実践できる能力が身につけば、看護師としての評価も上がります。自身の看護スキルをより活かせる環境で働きたい場合には、転職もひとつの選択肢となるでしょう。スマイルナースでは、31,000件以上の豊富な求人を公開しています。看護師業界に詳しいコーディネーターが、あなたの希望に合う求人をご紹介します。お気軽にご登録ください。