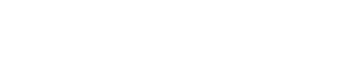MMT(Manual Muscle Test:徒手筋力テスト)は、筋力評価の方法のひとつで、医療現場で広く使用されています。特別な機器を使わず、徒手で評価ができるこの手法は、医療従事者にとって重要なツールです。
本記事では、MMTの基礎知識から評価基準、実施時の注意点、症例を踏まえた活用方法まで詳しく解説します。
MMTとは?

MMTは「Manual Muscle Test(徒手筋力テスト)」の略で、対象者の筋力を手で確認し、0~5の6段階で評価する検査方法です。
MMTを使用するシーン
MMTは、整形外科の外来をはじめ、救急の初期対応や集中治療室などさまざまな臨床現場で活用されています。特に機器を必要としないため、ベッドサイドでも簡単に実施できるのが特徴です。
おもな目的は、筋力や神経障害の有無、治療やリハビリの効果判定です。医師が診断に使う以外に、看護師や理学療法士、作業療法士も患者さんの日常生活動作の状況を把握したり、リハビリを提供したりするのに用います。
MMTでわかること
MMTは、筋力の程度を部位別に把握するだけでなく、日常生活動作を自立して行えるかどうかの確認、神経障害がどの部位にあるかを推定する目的でも行われます。
健康的な日常生活を営むには、少なくともMMTで3以上の評価が必要とされており、介護の必要性を判断するうえでも重要な指標となります。
MMTの評価基準とは
MMTの評価基準は、以下の6段階で構成されています。
| 評価 | 基準 | |
| 5 | Normal | 強い抵抗を加えても、運動域全体にわたって動かせる |
| 4 | Good | 抵抗を加えても、運動域全体にわたって動かせる |
| 3 | Fair | 抵抗を加えなければ、重力に抗して運動域全体にわたって動かせる |
| 2 | Poor | 重力を除くと、運動域全体にわたって動かせる |
| 1 | Trace | 筋の収縮はみられるが、関節運動は生じない |
| 0 | Zero | 筋の収縮がまったくない |
リスト
MMTの評価表は、筋肉の部位ごとに筋力や萎縮の有無、左右差などを記録するシートです。
評価項目には、僧帽筋・三角筋・上腕二頭筋・腸腰筋・大腿四頭筋などがあり、各部位に対して0~5の6段階で筋力を判定し、左右別に記録します。
以下は、一般的なMMTの評価表です。
| 右 | 筋肉の部位 | 支配神経 | 左 | ||
| 筋力 | 萎縮 | 筋力 | 萎縮 | ||
僧帽筋 | C2,C3 | ||||
| 三角筋 | C5 | ||||
| 上腕二頭筋 | C5,C6 | ||||
| 手根伸筋 | C6 | ||||
| 上腕三頭筋 | C6,C7 | ||||
| 手根屈筋 | C7 | ||||
| 指伸筋 | C7,C8 | ||||
| 指屈筋 | C8 | ||||
| 母指球筋 | C8,T1 | ||||
| 小指球筋 | C8,T1 | ||||
| 腸腰筋 | L1,L2 | ||||
| 股内転筋 | L2,L3 | ||||
| 大腿四頭筋 | L4 | ||||
筋肉の名称、支配神経、左右の筋力と萎縮の有無を一覧で確認できるため、筋力の変化を追いやすく、リハビリの効果判定や看護記録としても有用です。
MMTを用いる際に気をつけること
MMTは簡便で汎用性の高い評価法ですが、検査者によって結果にばらつきが出ることがあります。正確な評価を行うためには、筋肉の機能を十分に理解すること、正しい手技を身につけておくことが重要です。
また、被検者に意識障害がある場合、被検者が適切に力を発揮できない状態では正しい評価がむずかしく、MMTを実施できるかどうか、慎重に判断する必要があります。
検査の流れ
MMTは、以下の手順で行われます。
まず検査前に、患者さんへ目的や方法を丁寧に説明し、十分な理解と同意を得ます。続いて、評価する筋肉が最も収縮しやすい体位をとり、筋群ごとに順番に検査を行います。
検査者は被検者に、対象となる筋肉(または筋群)を収縮させ、その状態を維持するよう指示します。次に、検査者が被検者の筋肉の伸張方向に徒手で抵抗を加え、収縮をどれだけ保てるかを確認します。その際、左右差や筋力低下・麻痺の有無も評価します。
たとえば上腕二頭筋の場合、被検者に肘を曲げた状態を維持してもらい、検査者は手首を支えつつ肘を伸ばす方向に力を加えて筋力の程度を確認します。検査中は被検者の表情や動作の反応をよく観察し、痛みや不快感がないか注意がすることが大切です。
また、MMTは0~5点の6段階の評価が基本ですが、中間評価として“4+”や“3-”などを用いる場合もあります。
MMTの検査を行う際の注意点

MMTの検査を適切に実施するためには、いくつかの注意点があります。これらを遵守することで、正確で信頼性の高い評価を行うことができます。
事前に検査の目的と方法を説明する
MMTを行うには被検者の理解と協力が不可欠です。検査前には必ず検査の目的、方法、所要時間について被検者に丁寧に説明し、同意を得ましょう。被検者の不安や疑問を解消することで、より正確な評価結果を得ることにもつながります。
被検者に抵抗を加える際は利き手を使う
MMTで検査者が被検者の筋肉に抵抗を加える際は、必ず利き手で行います。毎回同じ手を使うことで、力の方向や強さを一定に保ちやすくなります。体重をかけすぎず、筋の走行や関節の動きに沿って、適切な力で抵抗を加えることが大切です。
体位交換は最小限にとどめる
高齢者や体力の低下した被検者の場合はとくに、検査による疲労や不快感を軽減するため、体位交換はできるだけ少なくしましょう。同一体位で評価できる筋はまとめて検査し、移動や姿勢の変更は最小限にとどめると、負担を軽減しながら効率よく進められます。
被験者のプライバシーに配慮する
筋肉の動きを細かく観察するMMTでは、検査部位を露出させる必要があります。カーテンで仕切る、必要最小限の露出にとどめる、タオルを活用するなど、被検者のプライバシーを守ることが大切です。
MMTを用いた評価例

ここでは、臨床でよく見られるケースをもとに、MMTの評価方法や判定の進め方を紹介します。検査の流れや筋力の評価方法を確認しながら、現場で活用できるよう理解を深めていきましょう。
症例1:
12歳の男の子。1年前より後頚部の凝りを訴え、12日前から左上腕の挙上困難としびれが出現した。MMTでは左三角筋2、上腕二頭筋3、他筋群も軽度低下を認めた。意識清明で歩行は可能。深部腱反射や感覚障害、前鋸筋異常は認められなかった。
症例1の評価
診断名:近位型頚椎症性筋萎縮症(CSA)
MMTで左三角筋2、上腕二頭筋3、他の筋も軽度に低下。右との差が明らかで、C5・C6神経根支配筋に一致する筋力低下パターンから、頚椎レベルでの神経障害が疑わしいと判断できる。
症例2
45歳の男性。デスクワーク中心の電気工事管理職。重い荷物を繰り返し持ち上げた後、腰痛と左下肢のしびれ・疼痛が出現した。MMTでは左中殿筋2、母趾・足趾伸筋4、長・短腓骨筋3を示す。意識清明。歩行器は使用可能だが、独歩は困難。
症例2の評価
診断名:腰椎椎間板ヘルニア(L5/S1)
MMTでの筋力低下はL5神経根支配筋に一致し、SLRテスト陽性からもL5/S1ヘルニアによる神経根圧迫が強く疑われる。
症例3
55歳の男性。有機リン製剤を内服し搬送。第25病日より両足の動かしにくさを訴え、第33病日には歩行困難となる。MMTでは両前脛骨筋0、腸腰筋4で、下肢に選択的な筋力低下が認められた。上肢は保たれ、意識清明だが、自立歩行は不可。
症例3の評価
診断名:有機リン中毒による遅発性多発神経炎(OPIDN)
MMTでの前脛骨筋0、腸腰筋4は、下肢の選択的な神経障害を示す。とくに前脛骨筋の麻痺により下垂足が生じ、歩行能力に大きな支障をきたしている。継続的なリハビリと装具使用が必要。
まとめ
MMTは、神経や筋肉の障害を評価するうえで欠かせない検査手法です。筋力の左右差や神経支配に基づくパターンを正確に把握することで、障害の部位特定や回復の見通しを立てるのに役立ちます。
看護師がMMTの基礎知識と評価スキルを備え、リハビリ職との連携や看護計画の立案に活用することは、患者さんの機能回復を支えるうえでも非常に重要だといえるでしょう。
看護師の求人探し・転職のことなら「スマイルナース」
MMTをはじめとする身体機能評価の知識、リハビリテーション領域での経験を活かしたい看護師には、スマイルナースの活用がおすすめです。スマイルナースは、看護師専門の転職支援サイトで、約26,000件の求人情報を取り扱っています。無料会員登録後は、専任のコーディネーターが希望条件を丁寧にヒアリングし、転職活動をサポートします。
機能訓練や慢性期ケアに関心のある方、働き方を見直したい方は、スマイルナースで気になる求人をチェックしてみてください。