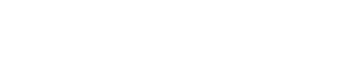看護学生が病院実習で立案することが多い看護計画。業務の効率化が進む近年は、多くの医療機関において看護診断に基づく看護計画がマニュアル化 されており、いざ看護師として 働きだすと計画をイチから立てる機会は少ないのではないでしょうか。
この記事では、看護計画の立案ステップについて詳しく解説します。改めて看護計画について振り返りたい人も参考にしてください。
看護計画とは?
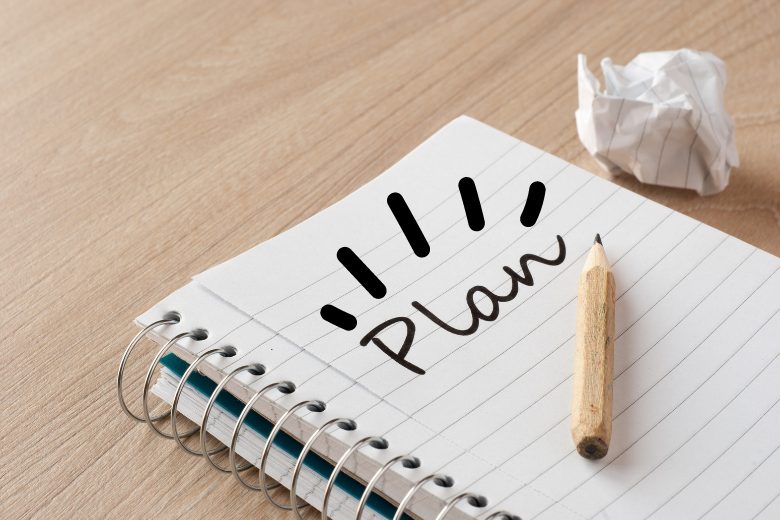
看護計画とは、患者さんの目標を達成するのに必要な行動を計画化したもののことです。計画を立てるにあたっては 、患者さんに関する情報収集やアセスメントの分析により導いた看護診断を用います。
看護計画はもともと1940年代のアメリカにおいて、看護師でないスタッフに対してケア計画を指示するためにつくられたものです。日本では1940~1950年にかけて、渡米した看護師により患者さんの問題解決を目指す過程(看護過程)として看護計画が紹介され、医療現場に広まっていきました。
看護過程を構成する要素
看護過程とは、看護師が患者さんにみられる看護問題の解決を図るときに使用する方法のことです。看護問題とは、患者さんが療養生活中に抱える問題のうち、 看護師の介入により解決を目指せるものを指します。看護師が立案する看護計画もまた看護過程のステップの1つです。
看護過程のステップは、アセスメント・看護診断・看護計画・看護介入・看護評価の5つから成ります。ここでは、看護過程を構成する各要素について詳しくみていきましょう。
| アセスメント | 患者さんの状態を把握するために、集めた情報を分析することです。看護問題を導きだすために欠かせない過程です。 |
| 看護診断 | アセスメントで分析した情報をもとに、患者さんが抱える問題を抽出します。 |
| 看護計画 | 看護診断により明らかになった患者さんの問題を解決するための計画を立てます。看護計画を構成する要素には、観察計画(OP)・援助計画(CP)・教育計画(EP)があります。 |
| 看護介入 | 看護計画で立案した内容を患者さんに対し実施する段階です。 |
| 看護評価 | 看護計画に基づいた介入により、目標の達成度を評価します。看護問題の解決に至らなかった場合は、さらに必要な看護計画を追加します。 |
看護計画に記載する項目
看護計画を立案する際は、次の内容を記載します。
・看護診断名(看護問題)
・看護目標
・観察計画(OP)
・援助計画(TP)
・教育計画(EP)
以降では、各項目の記載内容について詳しくみていきます。
1.看護診断名(看護問題)
看護診断では、患者さんが抱える看護問題(看護診断名)を抽出します。看護診断名は、チーム内の看護師が共通の認識を持てるものでなければなりません 。多くの場合、看護問題を選ぶにあたっては 、北米看護診断協会(NANDA-I)によって承認された看護診断名のリストを用います。 看護診断名を記載する際のポイントは以下です。
・看護診断名の抽出は、患者さんの抱える重要な看護問題から列挙する
・各看護診断名にナンバー(#)付けをし、優先度の高いものを1番上に記載する
・患者さんが抱える看護問題を定期的に見直す
2.看護目標
看護目標では、看護計画に基づいた看護ケアによって期待されるゴールを設定します。看護目標には大きく分けて、長期目標と短期目標があります。記載する際のポイントは以下です。
・長期目標には看護診断名の解決 について記載する
・短期目標には看護問題を構成する関連因子の解決 について記載する
・長期目標と短期目標を記載する際に、問題解決日を設定する
・それぞれの目標は、評価しやすいように具体的な内容にする
たとえば看護診断名が「#食欲不振」の場合、長期目標は「食欲不振が解決する」、短期目標は「病院食を5割以上摂取できる」といった内容になります。具体的な解決策は3.~5.の計画欄に記載します。
3.観察計画(OP)
観察計画(OP)には、看護問題の状況を把握したり評価したりするのに必要な項目を記載します。看護計画で記載する観察計画(OP)は、看護診断名によっても異なります。
4.援助計画(TP)
援助計画(TP)は、患者さんの看護問題の解決や看護目標を達成するのに必要な看護ケアのことです。看護計画の援助計画(TP)には次のものがあります。
上記の援助計画はざっくりした内容ですが、看護問題に沿ってさらに詳しい内容に落とし込む必要があります。
5.教育計画(EP)
教育計画(EP)は、患者さんの看護問題の解決や看護目標の達成に必要な指導・教育内容のことです。看護計画に記載する主な教育計画(EP)は以下です。
・薬の管理についての説明
・退院後の生活に関する指導
・インスリン自己注射、自己導尿などの手技の指導
・患者さんの家族に対する教育や指導
また、看護計画における教育計画(EP)も援助計画(TP)と同様に、看護診断名や看護問題に合わせ、 詳しい内容を作成する必要があります。
看護計画の記載例
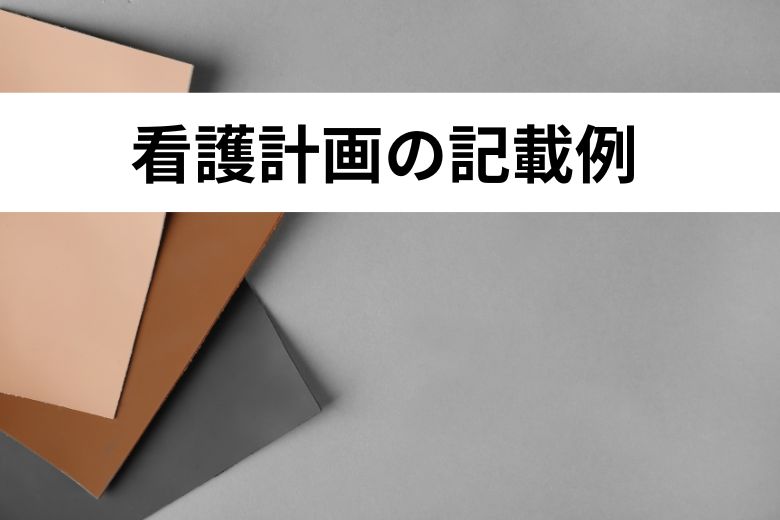
ここでは、具体的な看護診断名をもとに、看護計画の記載例を紹介します。
| 看護診断名 | #転倒・転落リスク状態 |
| 看護目標 | 長期目標:退院日までに転倒・転落事故が起こらない 短期目標:ベッドから離れるときにナースコールを使用できる 評価日:〇月〇日(次回のカンファレンス日) |
| OP(観察計画) | ・バイタルサイン ・年齢、筋力の程度、歩行状態 ・認知症の有無とその程度 ・転倒・転落歴の有無、転倒・転落の危険に対する認識 ・睡眠状況、睡眠薬の使用の有無 ・麻痺の有無と部位、痛みの有無と部位 ・自助具の使用の有無 ・貧血に関する血液データ(Hb,Ht,RBC) ・輸液ラインやチューブ類の有無 ・ベッド周りの環境 |
| TP(援助計画) | ・患者さんがベッドから離れる際は、見守りのために付き添いを行う ・ベッドの高さの調整、ベッド柵の利用(3点柵) ・ベッドストッパーの確認 ・ナースコールを患者さんの手元に置く ・検査時は車椅子への移乗を行う ・転びにくい靴を選ぶ ・必要に応じて離床センサーを設置する ・ベッド周りの環境整備を行う ・輸液ラインやチューブ類が足元に引っかからないように整理する ・必要に応じて、夜間用に尿瓶やポータブルトイレを設置する |
| EP(教育計画) | ・入院中の転倒や転落により、頭を強く打つなど命に関わるリスクがあることを説明する ・トイレなどベッドから離れるときは、必ずナースコールで看護師を呼ぶように説明する ・スタッフの介助が必要なときは、遠慮なく依頼するように説明する ・スリッパではなく靴を履くように説明する ・前開きの浴衣ではなく、パジャマを着用するように説明する ・ナースコールを使用しない場合は、離床センサーを使用する旨を患者さんや家族に説明する |
「転倒・転落リスク状態」は、高齢の患者さんであれば誰にでも起こりうる看護問題です。特に、入院により生活環境が変わると、夜間にせん妄を起こす人も少なくありません。持病や既往歴に合わせて、患者さんに合わせた看護計画を立案していきましょう。
まとめ
看護計画は、患者さんが抱える看護問題の解決を目指すために必要な看護ケアについて記載したものです。看護計画の立案は日々の業務に関わるものですが、多くの医療機関では業務効率を考慮し 、マニュアル化 されています。
「看護計画の立案は学生時代以来していない」と いう看護師も、看護計画のプロセスをもう一度確認し、改めて振り返ってみるとよいでしょう。
看護師専門の転職エージェント「スマイルナース」では全国の豊富な求人情報 を扱っています。看護師の求人情報だけでなく、看護の専門知識や転職にまつわる有益な情報も配信していますので、ぜひチェックしてみてください。